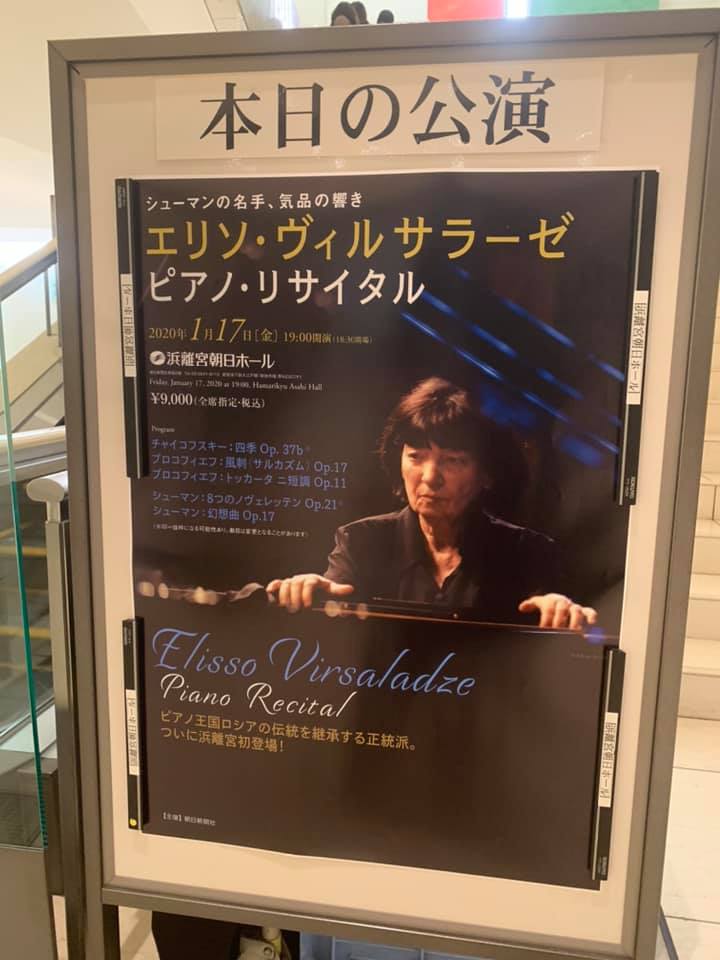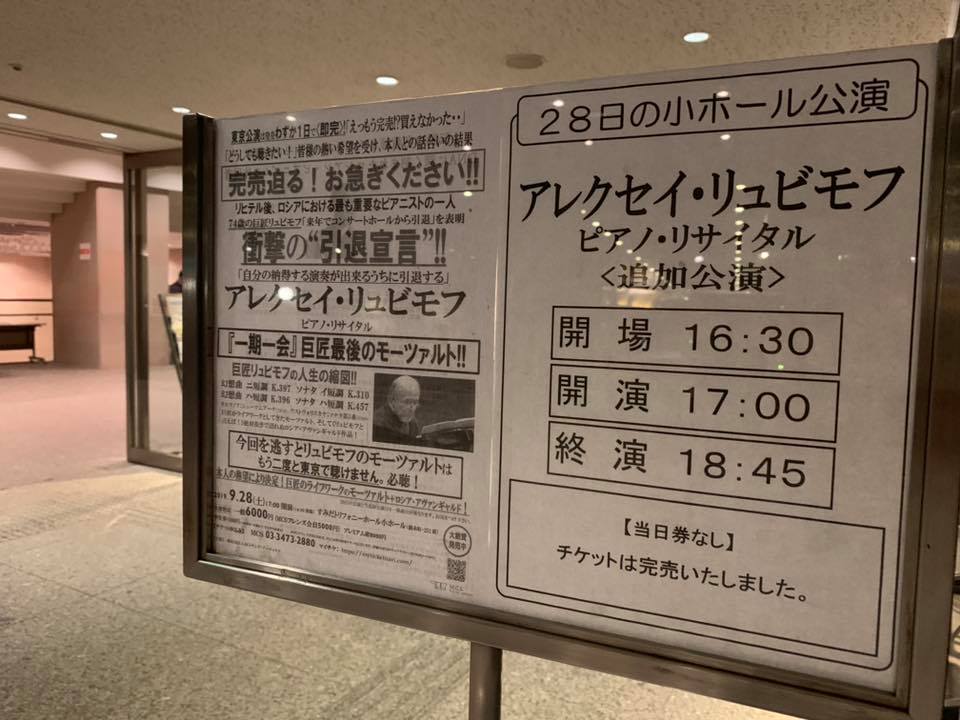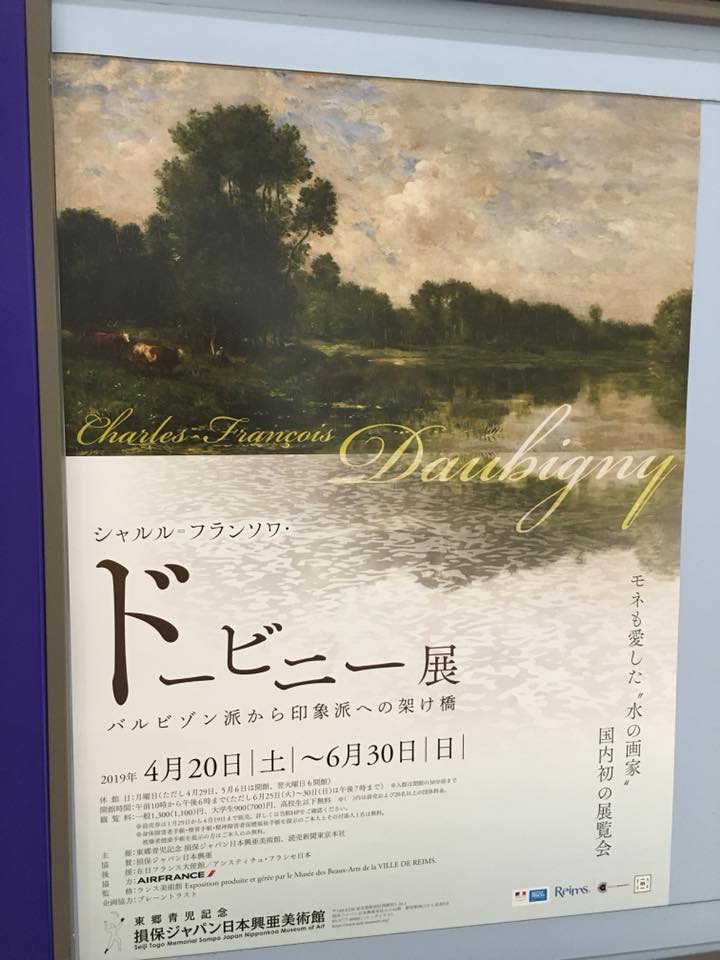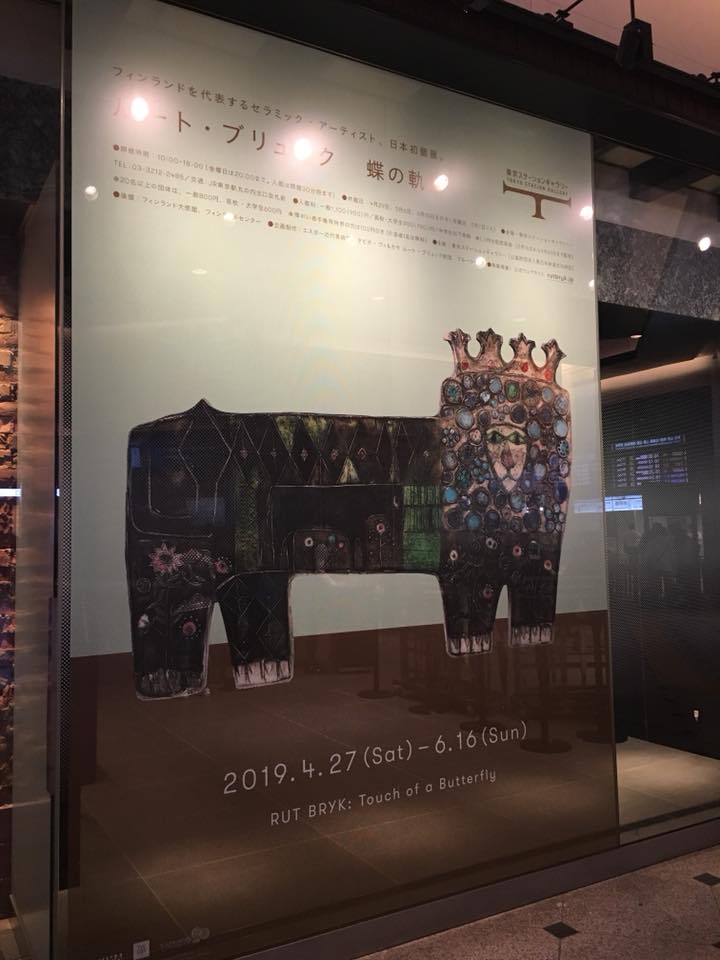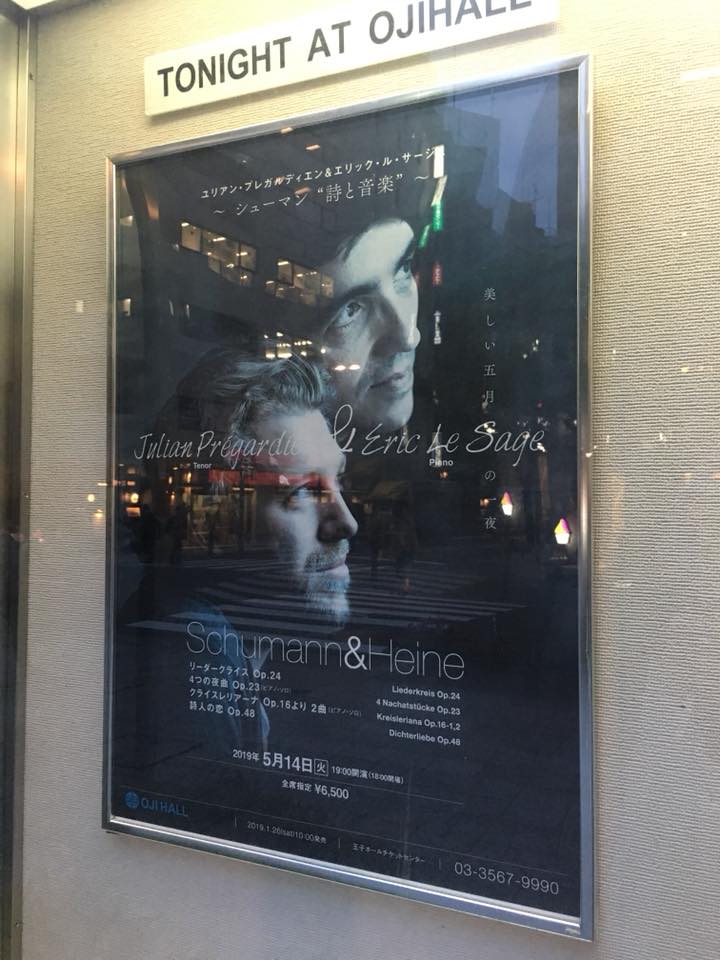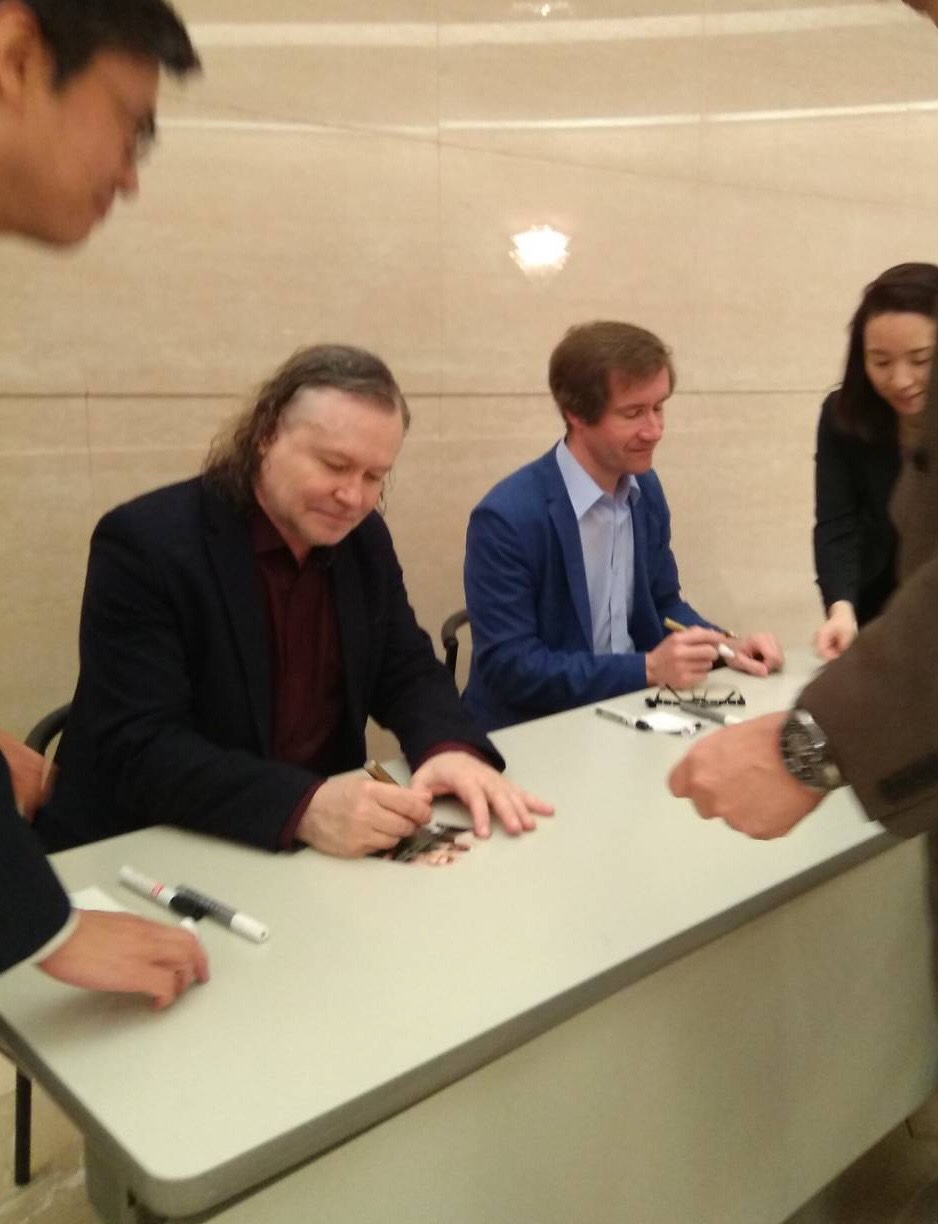梅雨入り前の先週、東京都美術館のクリムト展と、国立新美術館のウィーン・モダン展を鑑賞した。
Exhibitions of Gustav Klimt @Tokyo Metropolitan Art Museum and Vienna on the path to modernism @The National Art Center Tokyo
まず都美術館の方は、今年没後100年になるクリムトの油彩画が25点以上も揃うという充実振り。クリムトといえば女性遍歴も多く、裸婦や愛し合う男女をシンボルにした作品が思い浮かぶが、そういった作品に辿り着くまでの経緯が分かるように、時代順にさまざまな作品が並ぶ。7人兄弟の長男で、14歳で工芸美術学校に入学。若い頃は肖像画も多く描いており、21歳で友人や弟と工房を設立し、室内・舞台装飾の分野で活躍。公的機関からの依頼も来るようになり、時の人となるが、次第に伝統への迎合を嫌うようになり、分離派を結成。黄金様式へと向かっていく。金工師だった父親と、同じく美術の道を歩んでいた弟のエルンストを30歳の時になくし、姉と母は鬱病を患っていたらしく、クリムトの絵に現れる不吉で不安定なモチーフに繋がっていく。
私にとって印象的だったのは、金色を使った派手で官能的な作品よりも、養子にしたという姪ヘレーネや、生涯を通してのパートナーだったエミリエ・フレーゲなど身近な女性を描いた肖像画。舞台装飾やポスターなど幅広い作品に取り組んできただけあって、自らデザインしたという額縁も含め、そこにはデザイン性の高さが現れている。モノトーンの色彩、シンプルな構図のなかで、女性らしさを際立たせる。肌の色や衣服の透けるような質感と、首筋や髪の生え際が強調される横顔ならではの視点が、クリムトが抱く女性へのただならぬ関心を表している。
目玉作品として展示されていた、首を取り恍惚の表情をした《ユディト》や、手鏡を持った《ヌーダ・ヴェリタス》は、絵よりも黄金の額縁やシラーの文章に目がいってしまい、期待していた《ベートーヴェン・フリーズ》も、ベートーヴェンの音楽やシラーの思想とはどうも結びつかず、今ひとつピンと来なかった。
ただ、大衆に迎合せずに自分の中の真実を追究する姿勢と行動が、世の中にインパクトを与えたという事実は実感できた気がする。
一方のウィーン・モダン展は、改装中のウィーン・ミュージアムから膨大な数のコレクションが来日。マリア・テレジアの肖像画から始まり、ウィーンの都市の変貌、オットー・ヴァーグナーの建築計画など、絵画だけでなく食器や家具、衣装やアクセサリーに設計図までが所狭しと並び、クリムトにたどり着くまでにかなりの時間がかかった。
こちらのクリムト作品は素描も多くあり、特に初期の寓意絵(ドイツ留学中、何処かの美術館で惹かれて買った絵葉書の《愛》という作品)に思いがけず出会えたのが嬉しかった。絵葉書には男女の姿しか写っていなかったのだが、その上部には2人の運命を示すような不吉な3つの顔があり、額縁は金色と深緑の丁寧な作りになっていた。こちらもやはり透けるような肌と、霧がかった色彩感が印象的。
そしてそのクリムトを尊敬し、クリムトもその才能を認めたエゴン・シーレの作品が素晴らしかった。10代で父親を失い、その現実を受け入れられずに必死で絵を描いたというシーレが、ゴッホの影響を受けて描いた画家の部屋やひまわり、パトロンだったレスラーの肖像画など、落ち着いた暖色系の色合いと、物を捉える線の独特な角度、そして丁寧で迷いのない塗りの線がそのままデザインになって、見事な一体感を成しているのが凄い。枯れたひまわりの背景の白色でさえ、強くなにかを訴えかけてくる。
その他にこの展示で充実していたのが、分離派やウィーン工房のポスターグラフィックで、字体、色合い、デザイン、どれを見ていても飽きないものだった。
また、ウィーンならではの作曲家たち ーー シューベルトの有名な肖像画や実際に使用していた眼鏡、シューベルティアーデの様子を描いたもの、ヨハン・シュトラウスやマーラーの彫像、シェーンベルクの肖像画、シェーンベルクが描いたアルバン・ベルクの肖像画(!)まで展示されているのには驚いた。
ウィーン・モダン展の後、同じ国立新美術館で開催中の日洋展に出品されていた、叔母 並木貴子の《輝きの大地 2019》を観た。これまでもこのシリーズの絵を観てきたけれど、委員賞を受賞しただけあって、黄色と黒のコントラストが効いており、余分なものが削ぎ落とされてきているのが分かる。大胆な筆使いに、気持ちの定まり、叔母の進化、新境地を感じることが出来て、とても嬉しかった。
〔facebookパーソナルページより転載〕