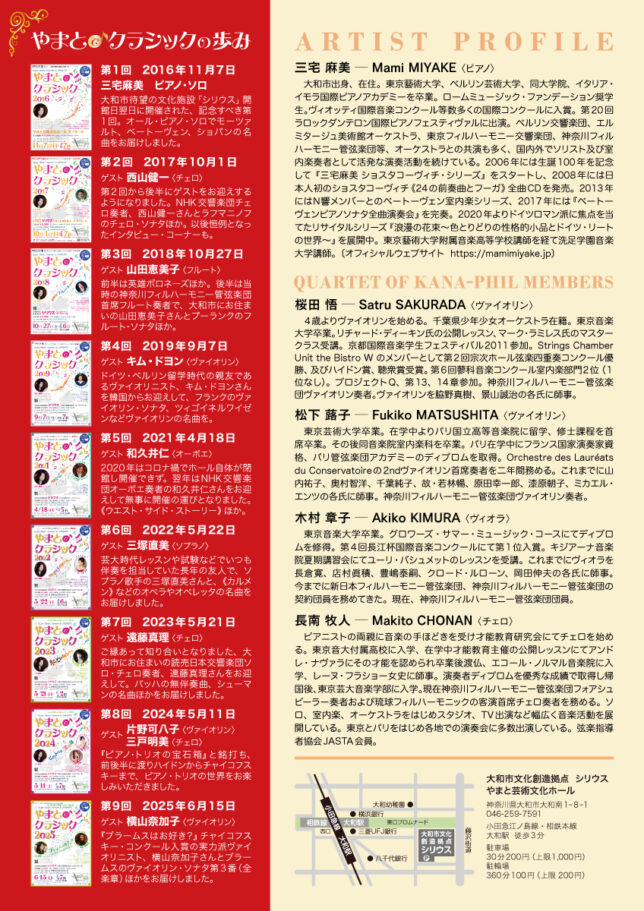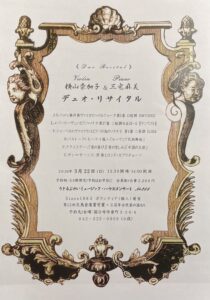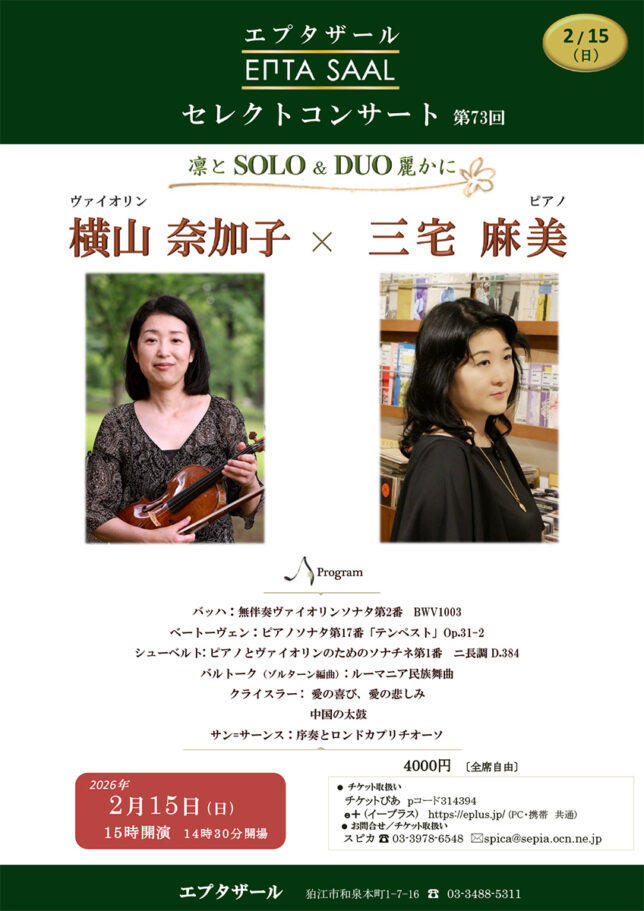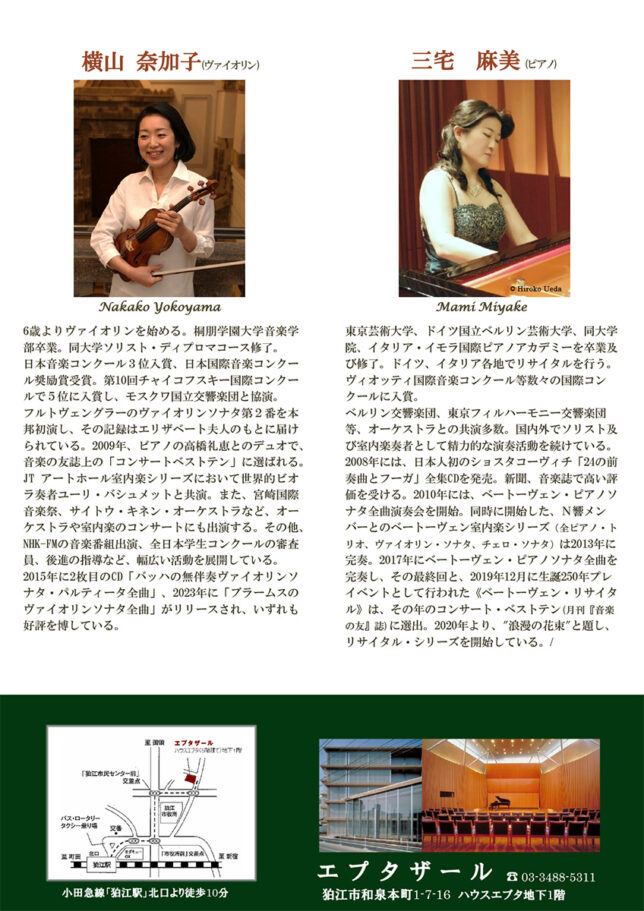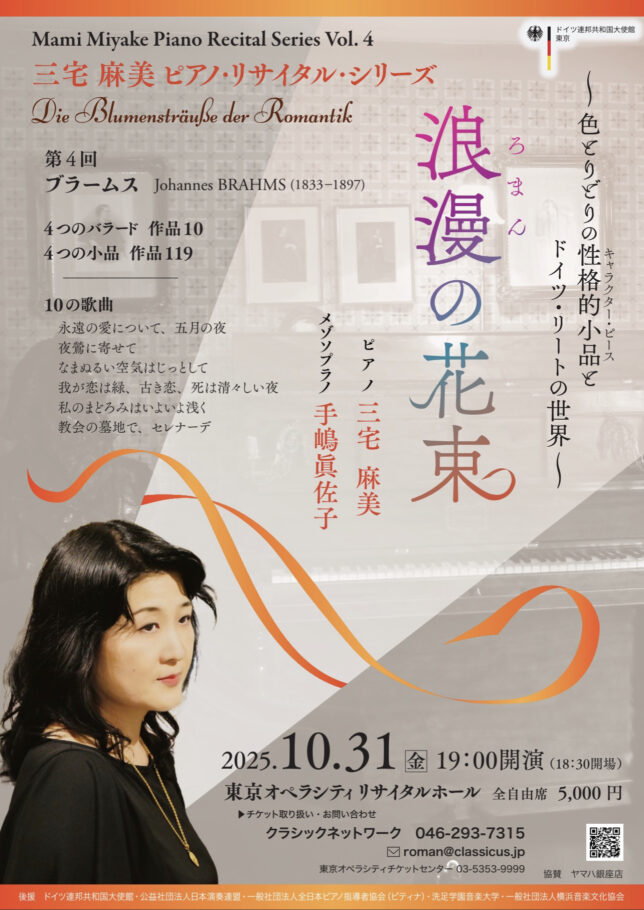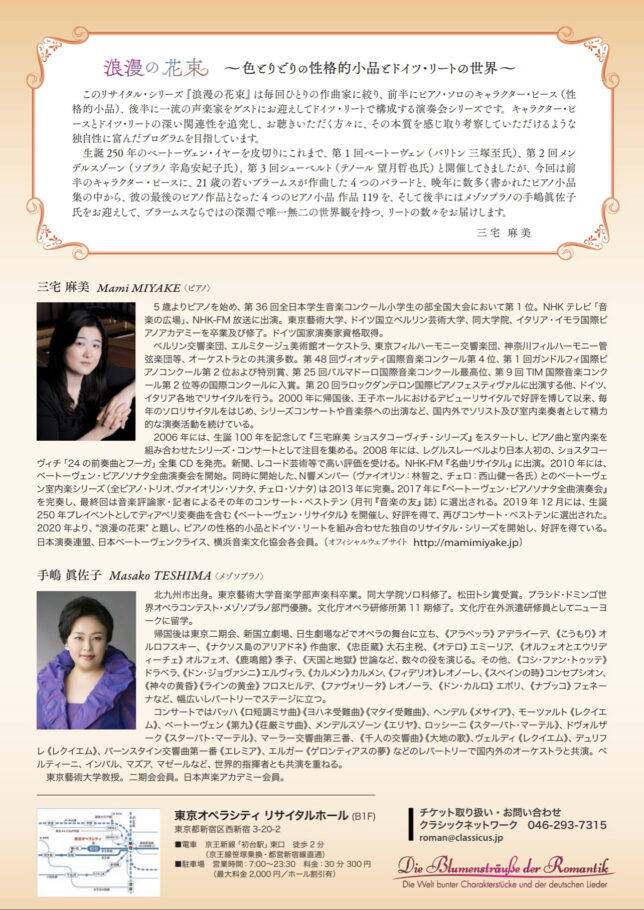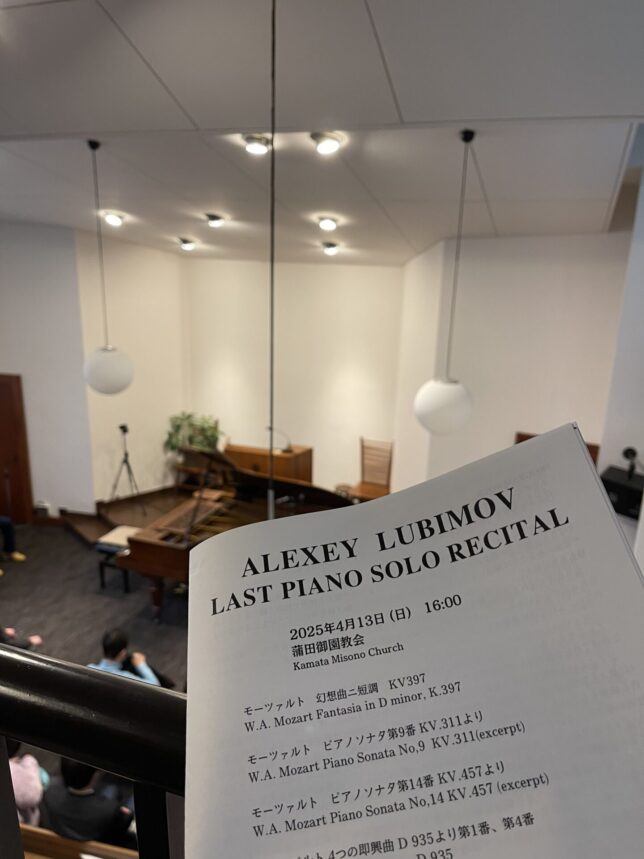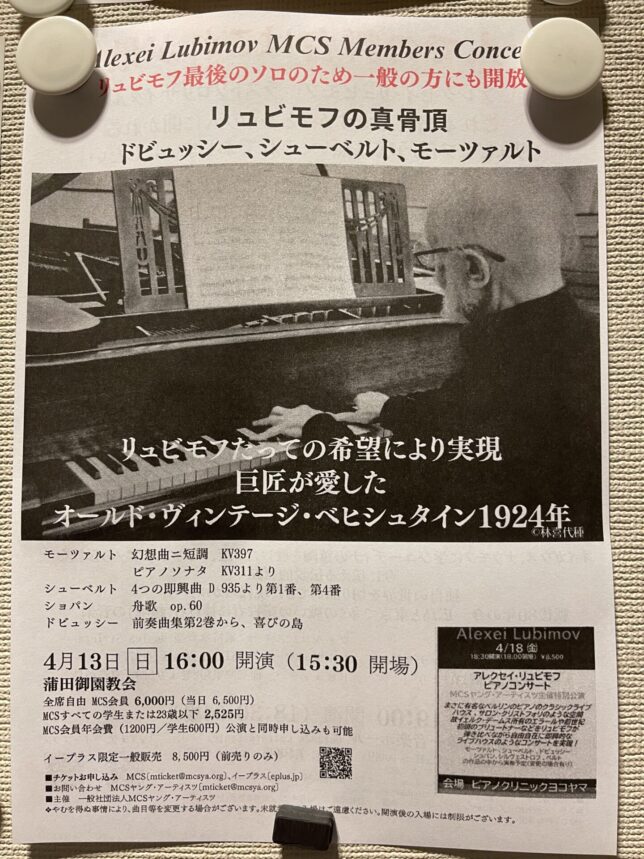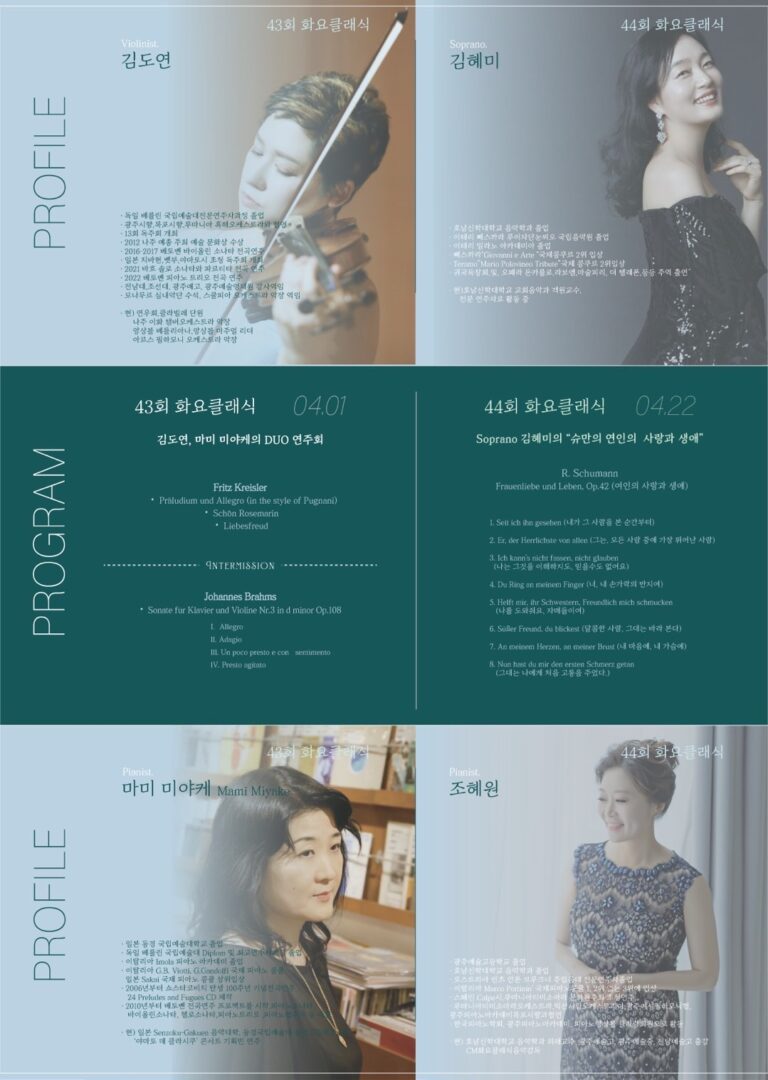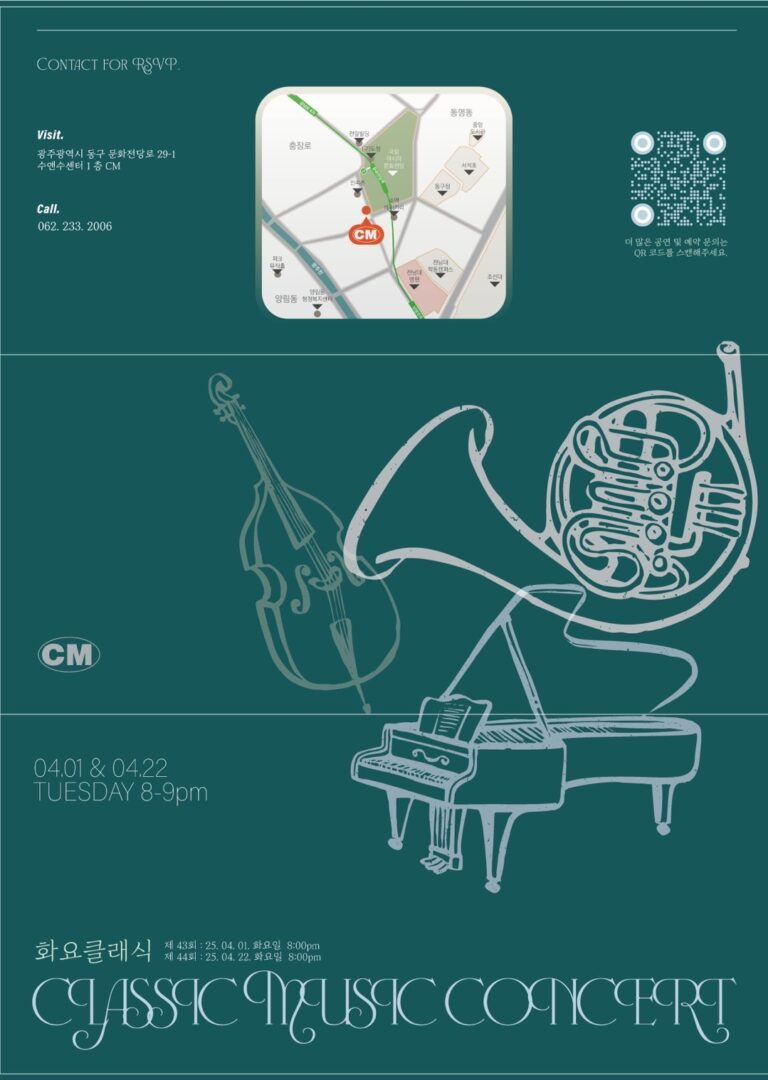【演奏会予定】2026年5月17日 やまとで♪クラシック2026
2026年5月17日日曜日 14時開演 13:30開場
やまとで♪クラシック〜みんなで楽しむ名曲コンサート〜第10回
『ピアノ協奏曲 with 弦楽四重奏 of 神奈川フィルハーモニー管弦楽団』
大和市文化創造拠点シリウス やまと芸術文化ホールサブホール
ドビュッシー アラベスク第1番
モーツァルト インテルメッツォ ニ長調
ボロディン 弦楽四重奏曲第2番より第3楽章ノクターン
ベートーヴェン ピアノ協奏曲第4番 ト長調 作品58
ゲスト かなフィルメンバーによる弦楽四重奏団
ヴァイオリン 桜田悟、松下蕗子
ヴィオラ 木村章子
チェロ 長南牧人
チケット予約・問い合わせ
クラシックネットワーク yamato@classicus.jp