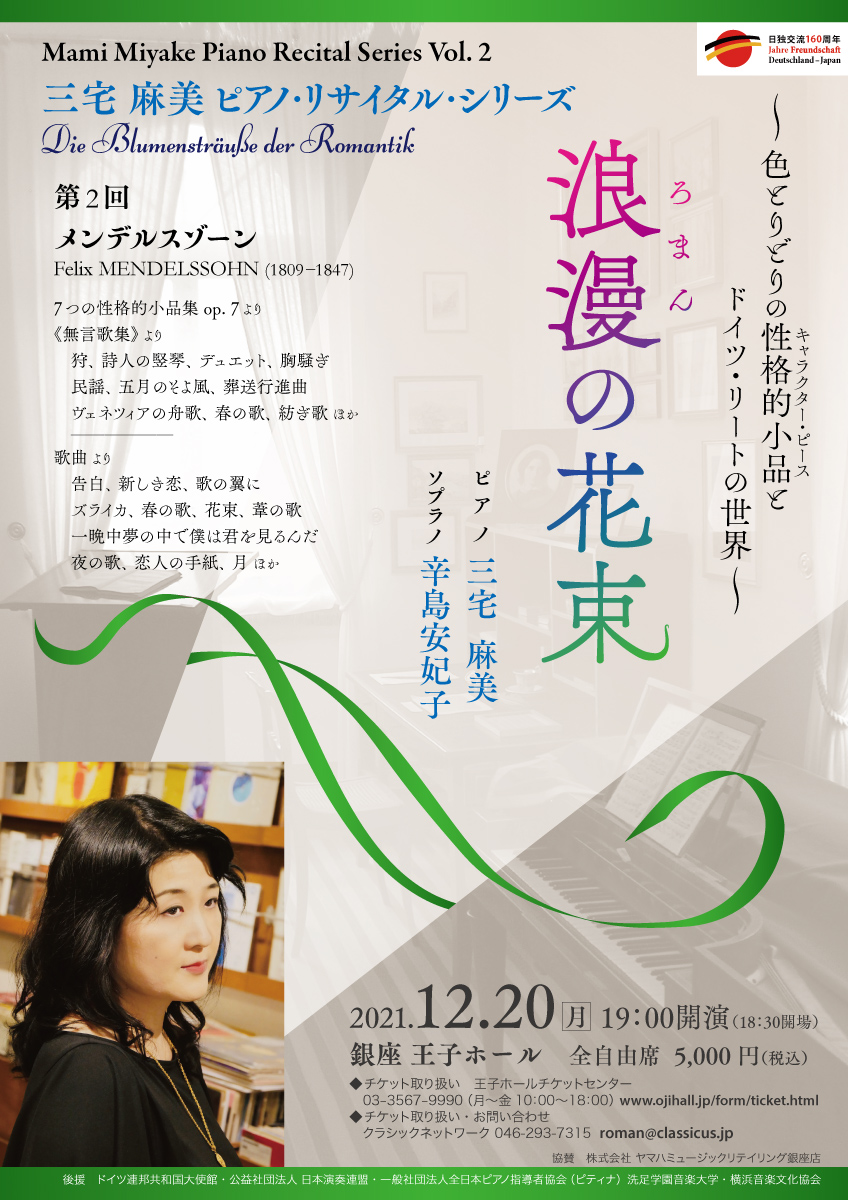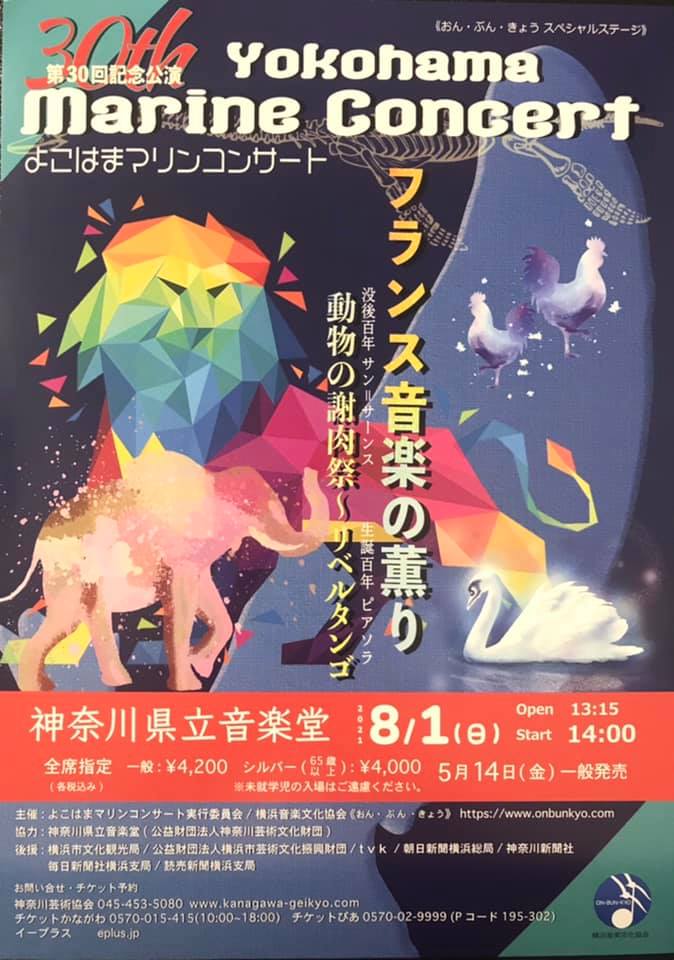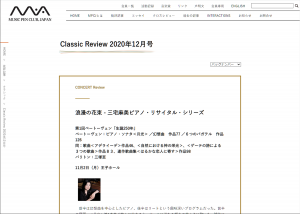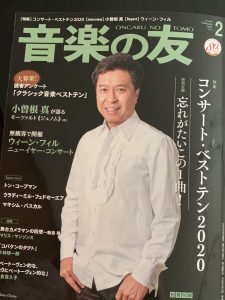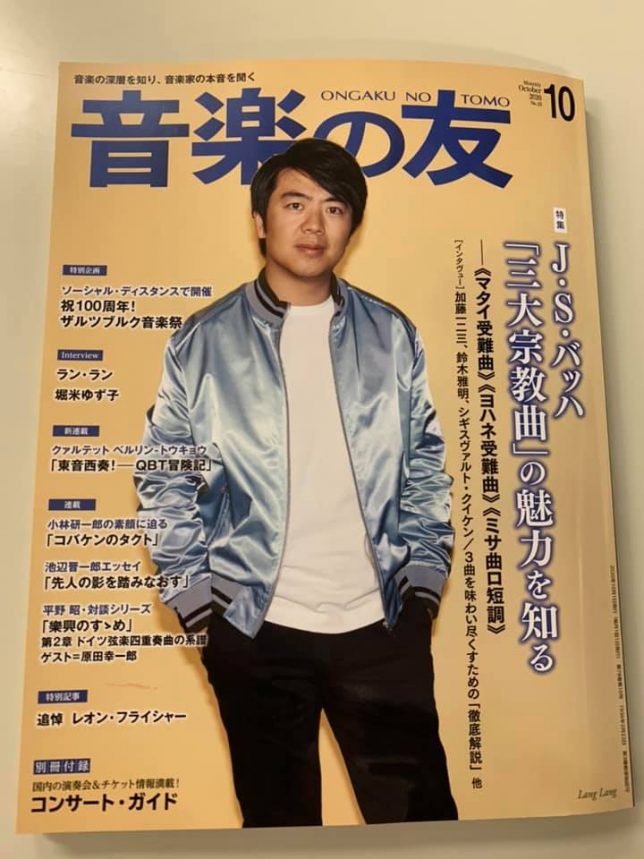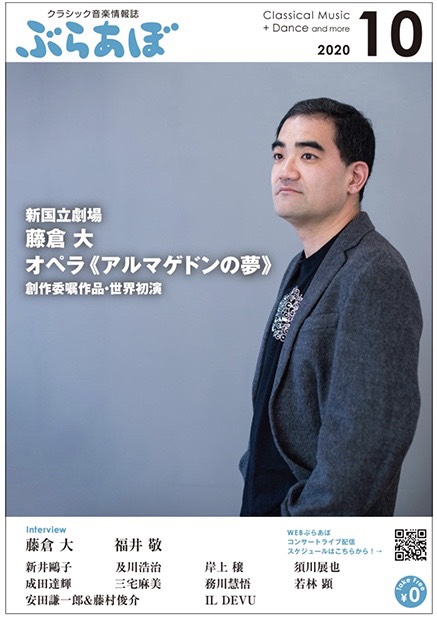【アート覚書き】渡辺省亭〜欧米を魅了した花鳥画〜展
このご時世でアート鑑賞もとんとご無沙汰している。それでも昨年末から春にかけては 琳派と印象派展@アーチゾン美術館(旧ブリヂストン美術館)、田中一村展@千葉市美術館、山陰に足を延ばした際に、島根県立美術館や足立美術館にも訪れて英気をいただいたが、先日は束の間の夏休みに三島にある佐野美術館に、渡辺省亭展を観に出掛けた。今春、藝大美術館で開催のはずが緊急事態宣言のため会期途中で中止となり、とても残念に思っていたところ、岡崎と三島に巡回することを知り、是非にと友人に車をお願いしていた。
渡辺省亭は明治から大正を生きた日本画家で、欧米での評価は高いものの国内ではまだあまり知られておらず、今回が初めての回顧展だそう。28歳の時に日本画家として初めてパリを訪れ、見事な筆捌きでマネやドガなどの印象派の画家に影響を与えたと言われている。5歳で絵の楽しみを覚え、浮世絵の模写をしたのち書を徹底的に3年間学び、そのあとに人物画を描き、そして真骨頂である花鳥画を描いていく。68歳で亡くなるまで生涯弟子を取らず、自分を売り込むことも嫌い、黙々と注文を受けた作品をこなしていたようだ。一昨年あたりだったか、赤坂・迎賓館の内部公開を観たときに、豪華絢爛な広間の壁にいくつもの花と鳥の図柄の七宝が飾られていたのだが、その元絵を描いたのが省亭だった。
さほど広くない展示室に足を踏み入れるとまず、チラシにも使われている『牡丹に蝶の図』がある。縦に一本伸びる添え木を巧く構図に取り入れ、枠の線を描かずに水彩のグラデーションで花びらの色と重なり合う質感を表現する。奥に朽ち行く花を描くことで、手前の紅白の牡丹の彩りがより一層感じられる。風に散りながらおしべがはらはらと地に落ちるさまをも描き、旬を迎えて咲き誇る花との対照を描く。蜜を吸うクロアゲハと遠くのモンシロチョウ、この絵では蝶よりも花の生命力が優っている。
その近くには『春野鳩之図』。春の野辺の草花たちを鳩の周りに散りばめ、枝垂れ桜と綿毛のタンポポ、そしてツクシの縦のラインを韻を踏むように生かしつつ、主役の鳩に目を向けさせる。三羽の鳩はそれぞれ色合いと体の向きが違うのだが、驚くのは良く見ると三羽とも口角が上がっていること。観ている側を自然と和やかな表情にさせる。
その隣の『雨中桜花つばめ図』もまた風情がある。花盛りの桜の木で燕三羽が雨宿りしているのだが、春雨の寒さに毛をふくらませた燕の体が印象的で、三羽の中でも後ろ姿の燕を最前に描くことで、その場の温度や寂しさまで漂わせている。
『月夜杉木菟之図』は、背後にそびえる大きな幹の木を見るからには、そのミミズク(トラフズク)まではかなりの距離があると思われるのだが、かなり大きな尺で描かれており、その存在感には目を見張る。思わずドイツ留学中に森の中で見たミミズクを思い出した。(かなり遠くにいるのにもかかわらず、目が合った瞬間嬉しいのと同時にドキッとした…)絵具を幾重にも薄く塗り重ねて実現した羽の色味や質感はまさに3Dのようにリアルで、その観察眼には恐れ入ってしまう。
63歳で描いた『猛虎の図』は、ずっしりと風格のある虎に今現在の自分を重ね、左上を見上げる凛とした眼差しに、未だ筆を持ち続けて自身の境地を開いていこうとする志が感じられた。
そして展示の最後には、数ヶ月前に所在が明らかになり今回急遽追加で展示された『春の野辺』。これは1918年に描かれ、蝶の彩色のみを残して絶筆となった作品。蓮華草の小さな花びらや細い葉の一枚一枚をこれまでよりも色濃く描き、その筆運びに一呼吸一呼吸を合わせて描かれたかのような凝縮感に胸を打たれた。
鑑賞後は美術館の敷地にある日本庭園を歩き、近くの柿田川公園で水を汲み、名物の鰻をいただいて帰りました。
〔facebookパーソナルページより転載〕