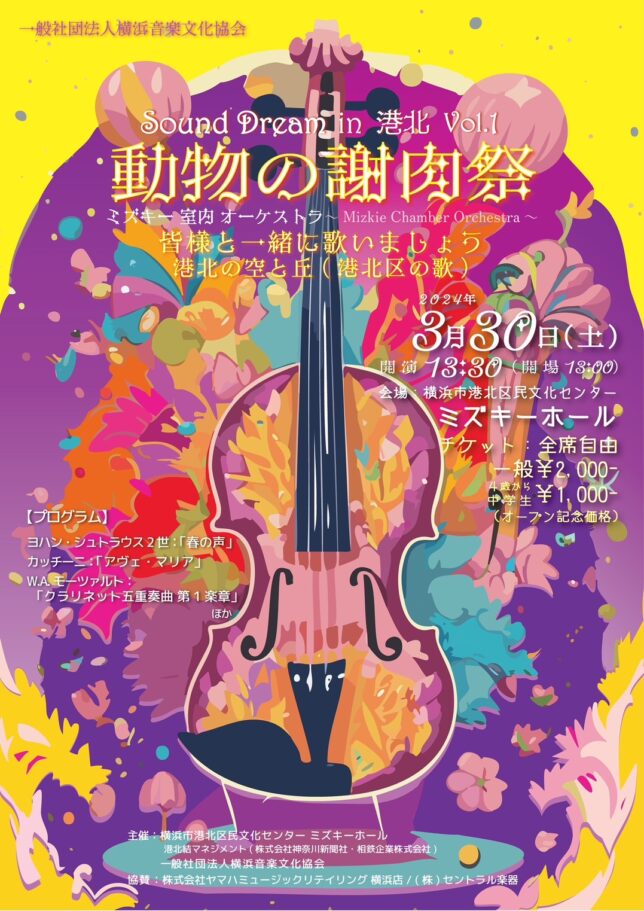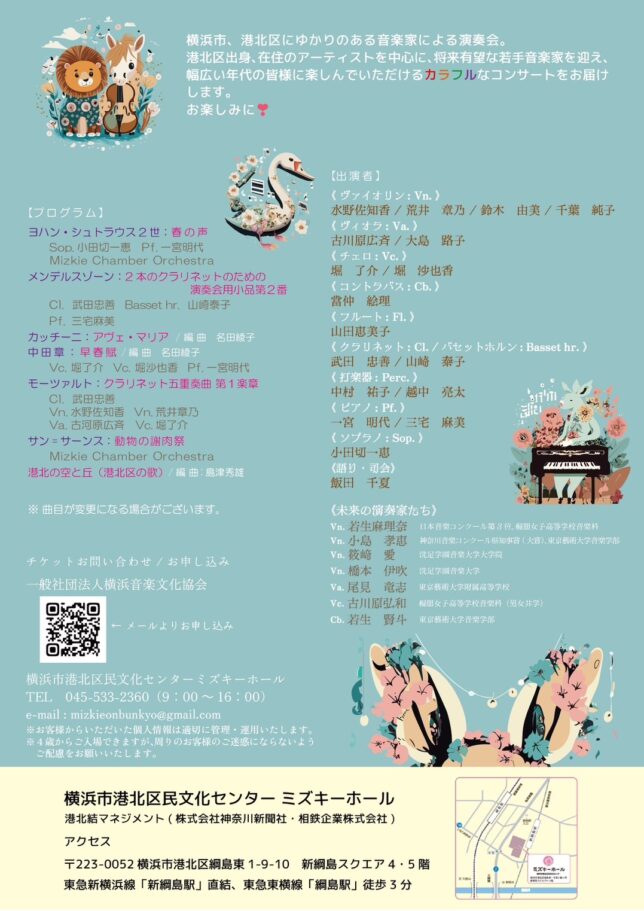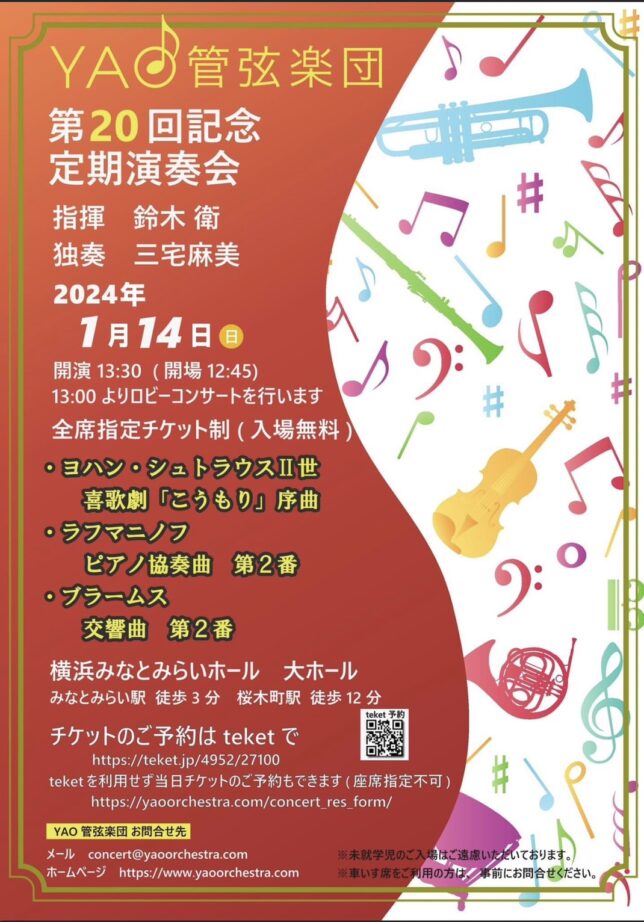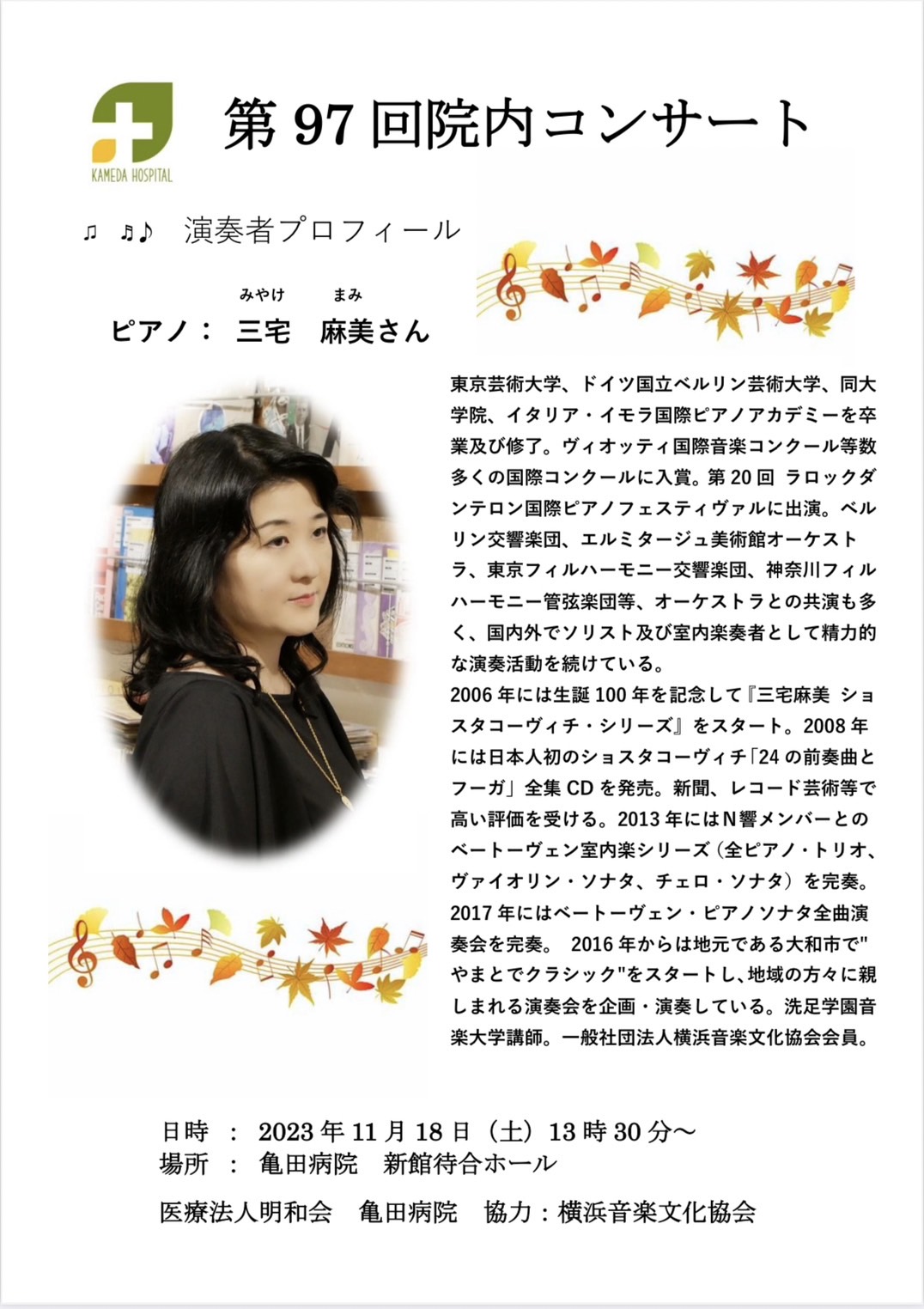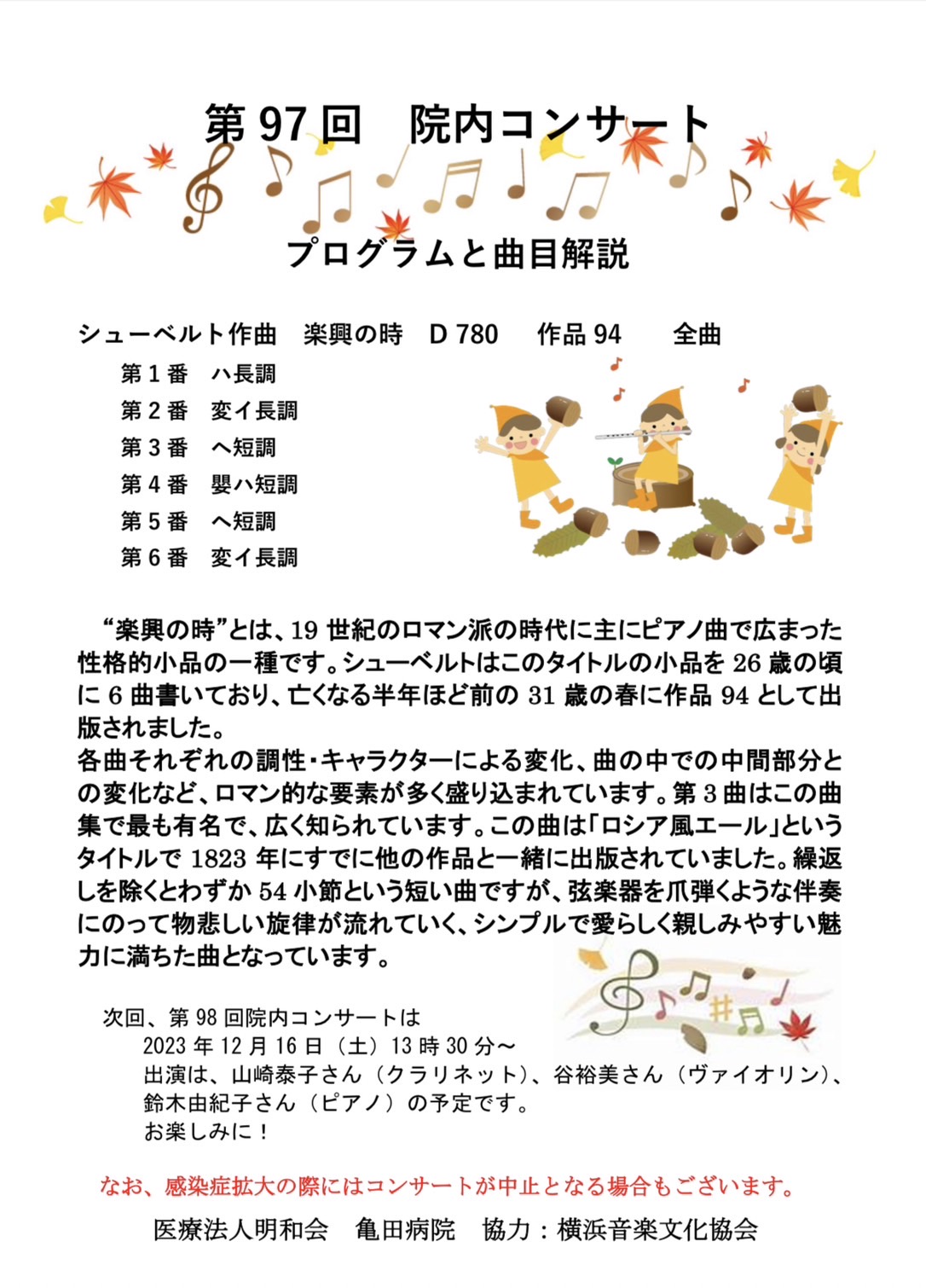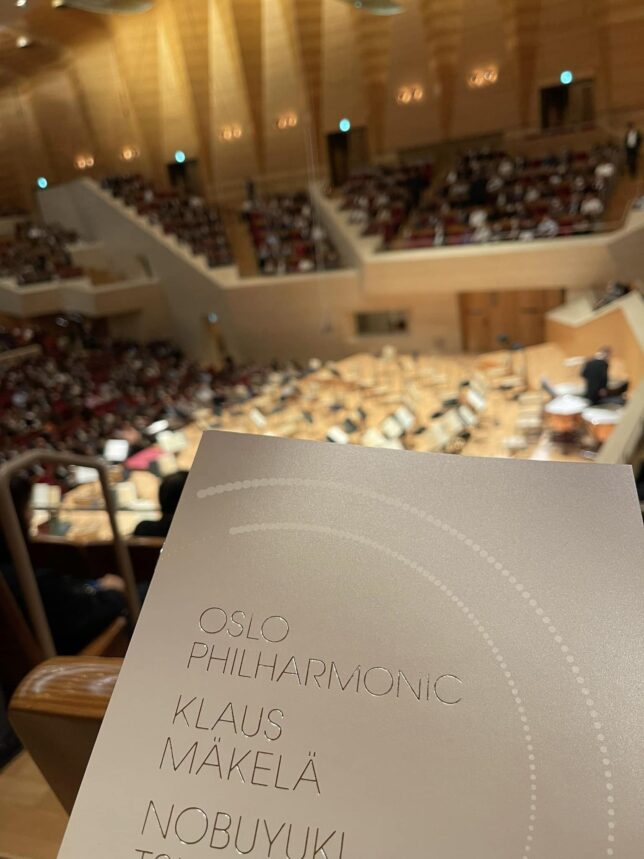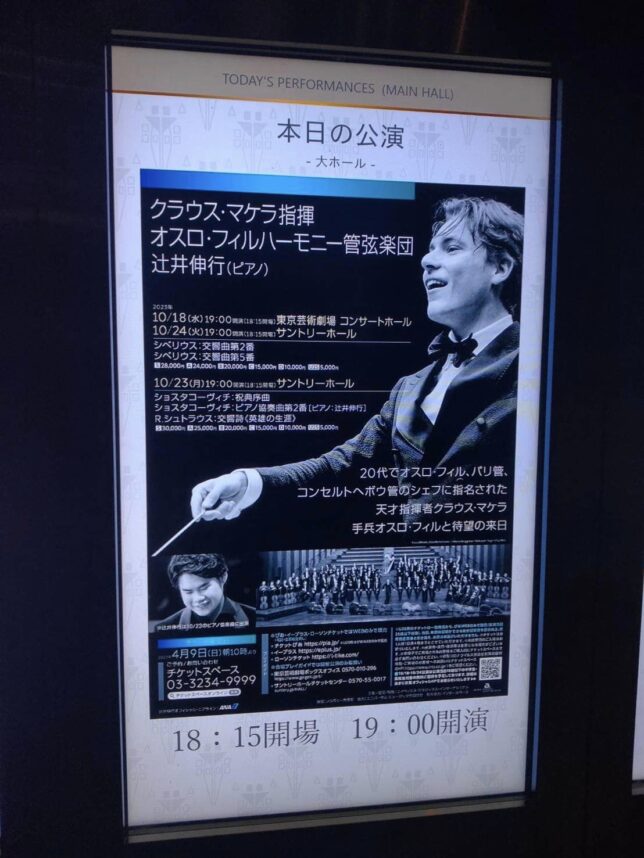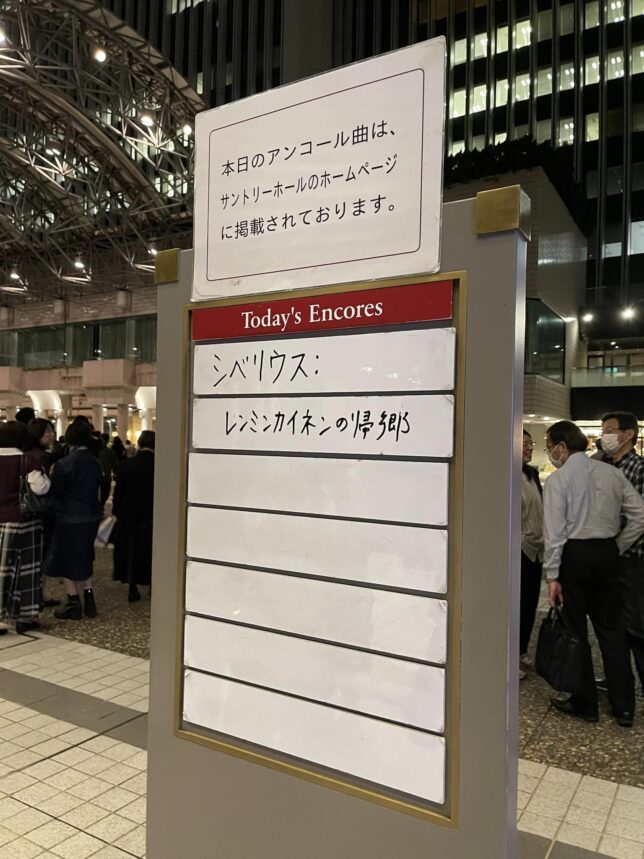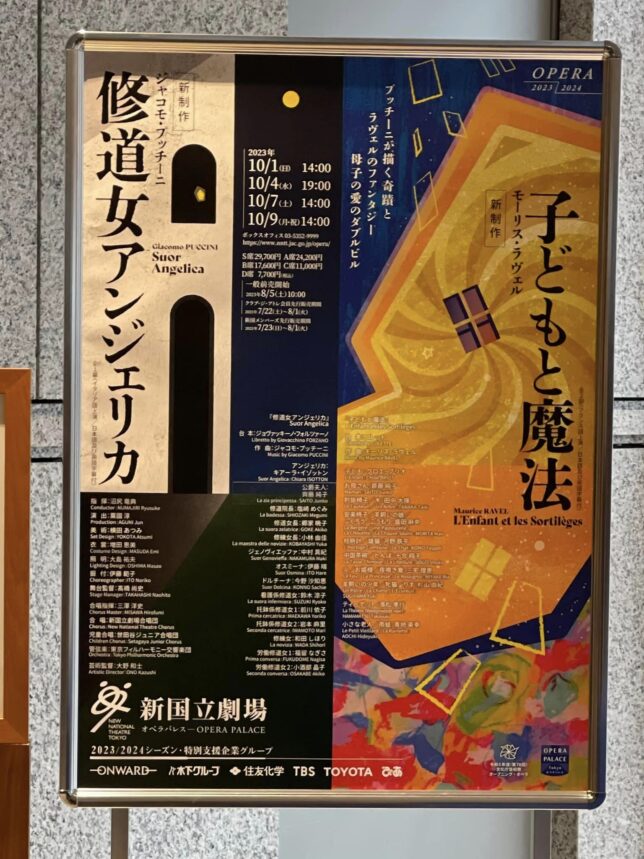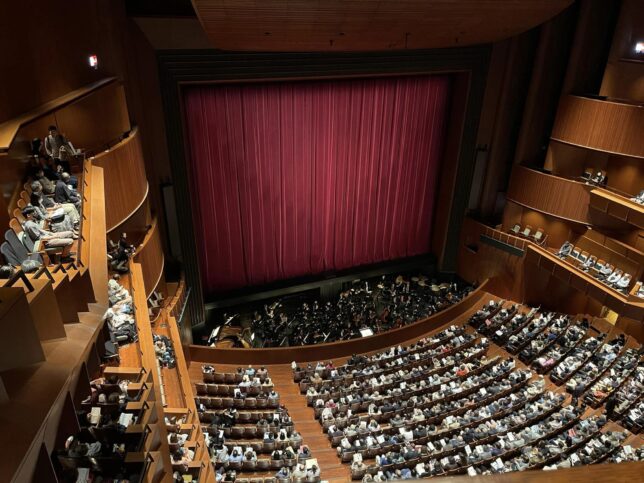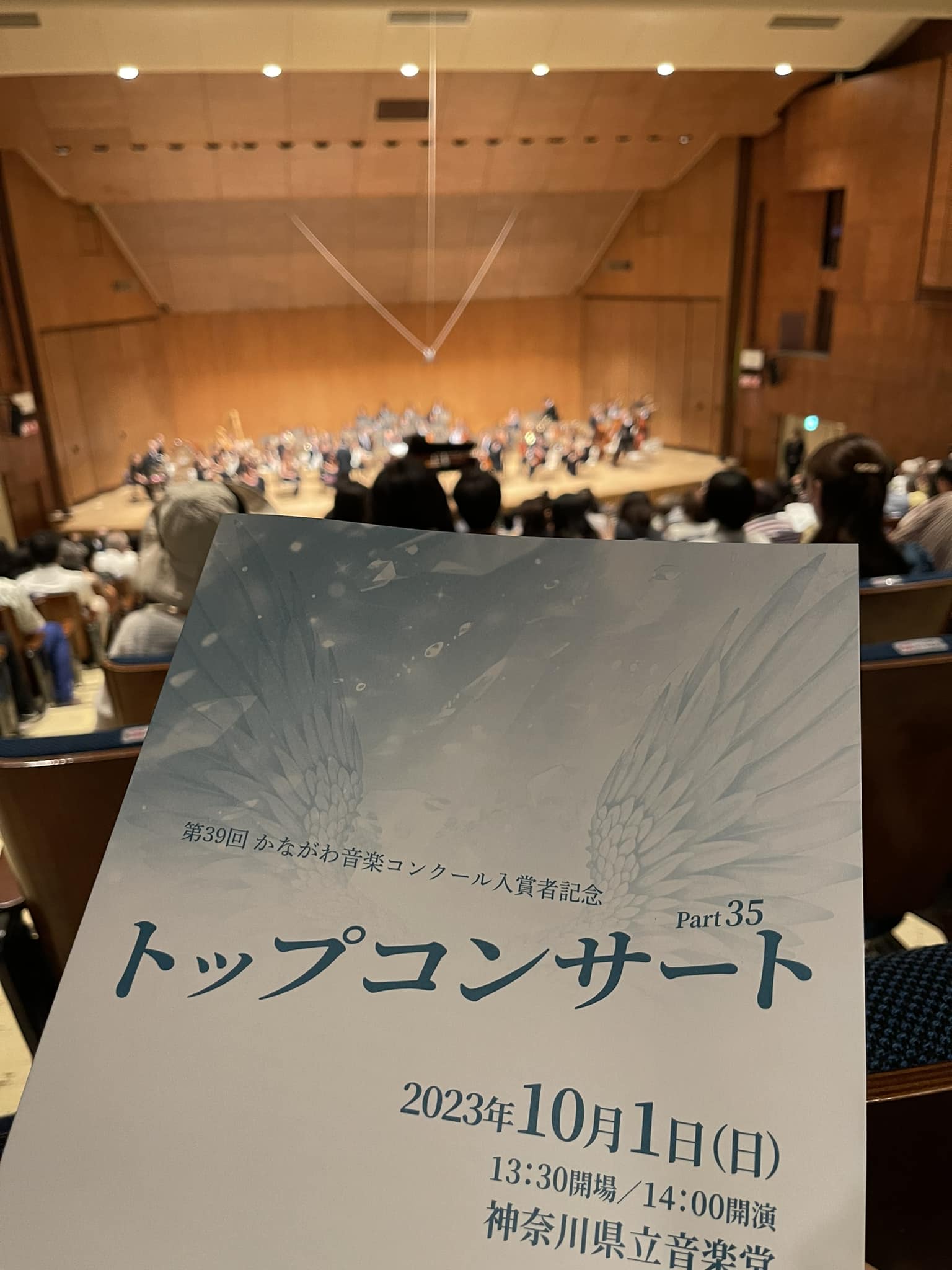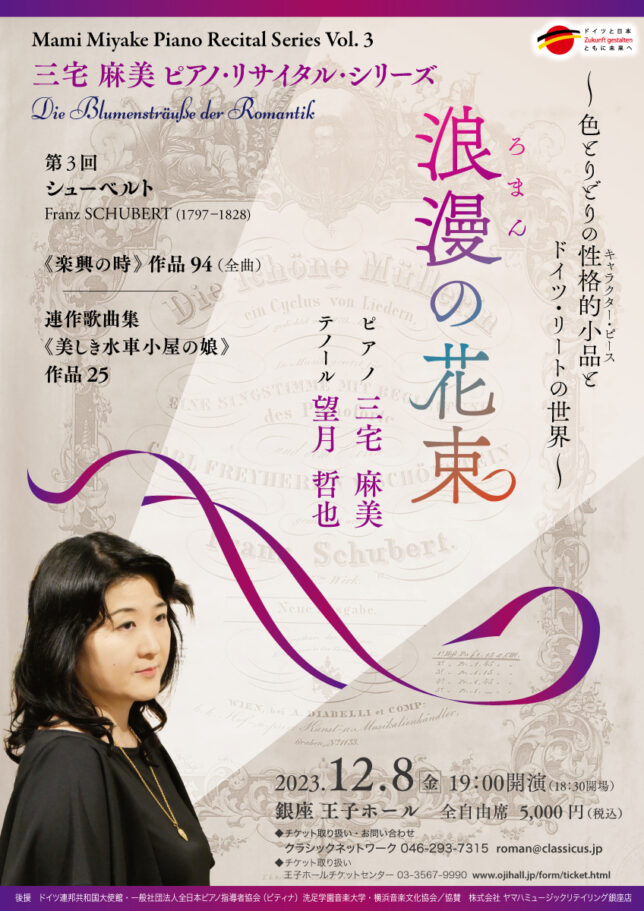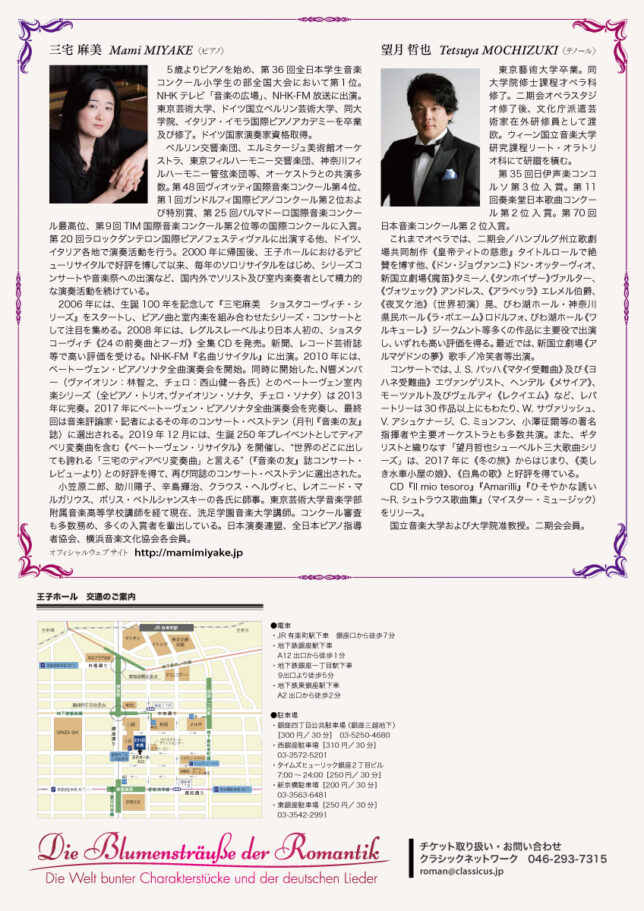【演奏会予定】2024年5月11日 やまとで♪クラシック2024

『やまとで♪クラシック2024』
~ピアノトリオの宝石箱~
2024年5月11日〔土〕19時開演
大和市文化創造拠点シリウス サブホール
ヴァイオリン 片野 可八子
チェロ 三戸 明美
ピアノ 三宅 麻美
ハイドン ピアノ三重奏曲《ジプシー風》
ベートーヴェン ピアノ三重奏曲《大公》
ドヴォルザーク ピアノ三重奏曲《ドゥムキー》
チャイコフスキー ピアノ三重奏曲《偉大な芸術家の思い出に》
ほか
チケットのご予約・お問合せ
クラシックネットワーク 046-293-7315 yamato@classicus.jp