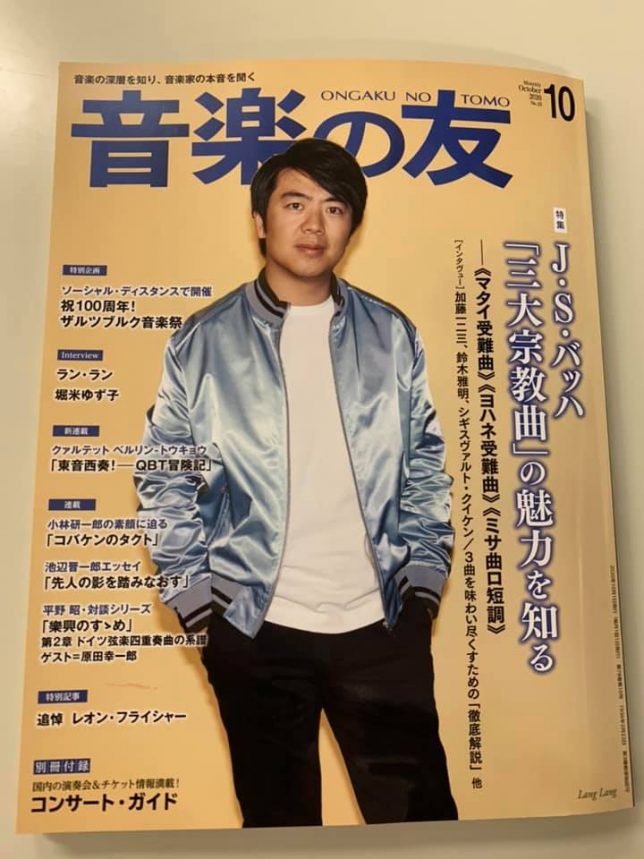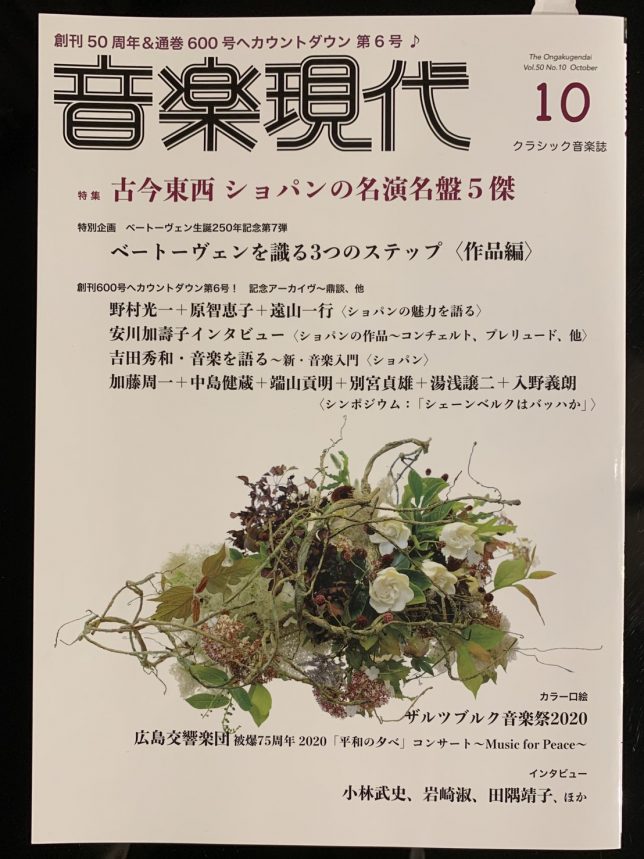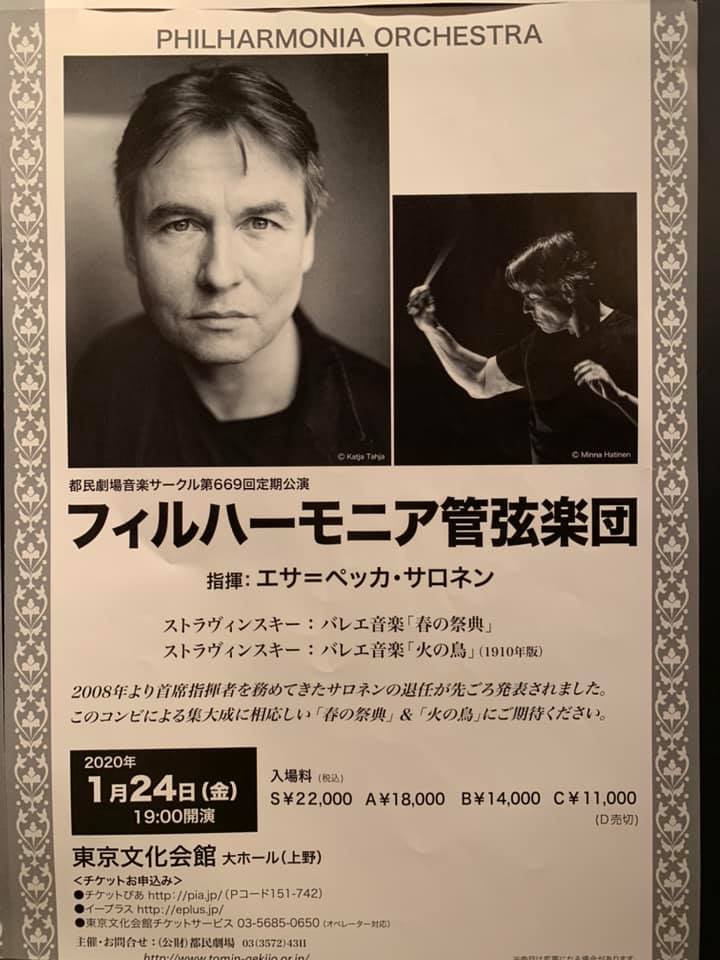【アート覚書き】永青文庫名品展
コロナ禍のせいもあってずっと叶わなかった美術観賞。本番からも解放されてようやく足を運ぶことができました(といってももう2週間前のことです)。
記念展示を開催していた永青文庫に初めて訪れたので、備忘録として…
副都心線雑司ヶ谷駅から都バスに乗り、3つ先の停留所、目白台三丁目で降りる。閑静な住宅街、木々に囲まれひっそりと佇む永青文庫は、肥後熊本五十四万石の細川家に代々伝わる文化財を保存し、研究・一般公開のために、16代細川護立が立ち上げたもの。神田川沿いまで斜面を利用して広大な庭園も隣接している。
今回の展示のお目当ては菱田春草(1874〜1911)の2枚の日本画。
まず、1909年に描かれた『落葉』は全部で12枚の屏風絵。日本画において、それまでのように線を使わずに描く「無線描法」ながら、いやそれゆえに木肌の立体感をここまで表現できることに驚かされる。葉元から葉先へ薄緑から色あせた黄土色、そして焦げ茶へと変化していく、枯れゆく落葉の時の移ろいと生の名残。枯れる様すら美しく、愛おしく描く。腎臓から来る目の病に侵されながら、虫食いの形や葉の反りなど、落ち葉一枚一枚に愛情を注ぐ。地面に描かれた四十雀のつがいはどんな状況でも命はたゆまず続いて行くたくましさをあらわし、細枝に留まり、さりげなく佇む色鮮やかなジョウビタキを描くことで、朽ちてゆく落葉の侘しさがより伝わってくる。常緑樹の松の緑の濃さは、色というより塗りの濃さとも言え、筆使いに生への執着が感じられる。画面の奥には、幻想的でありながら凛とした存在感を感じさせる木々等、いくら見ていても飽きない。
そして、何年前だろうか、近代美術館での菱田春草展以来の再会となる『黒き猫』。『落葉』を描いた翌年、死の前年に書かれた猫の絵。視線はまず黒猫に注がれ、その歌舞伎役者のような鋭い眼差しや、左右に開いた両耳から、猫自身の緊張感を感じとることができる。そして背景や木肌との輪郭のぼかしで巧みに表現したフォルムや、指先の丸みのやわらかな質感に触れる。猫の上に目を向けると、描かれた柏の葉の形の良さに魅了される。どの葉も表を向いているのに、その照らし方や微妙な大きさの差異、虫食いの形などの変化に趣を感じる。そして全体を観ると、深い茶緑と金色、猫の黒のコントラストが見事に一枚に収まっている。
横山大観の作品も多かったが、なぜかいつもあまり惹かれない。竹内栖鳳の描いた猿の掛け軸は、開いた両腕とその表情がなんとも言えない脱力感を与えてくれて微笑ましく、彼の生き物に対する審美眼をあらためて感じさせてくれた。他に国宝の日本刀や重要文化財の仏像、陶器など所狭しと展示されていた。
観賞後は、秋晴れの庭園をのんびり散策して、神田川沿いを江戸川橋まで歩いて帰路につきました。
〔facebookパーソナルページより転載〕