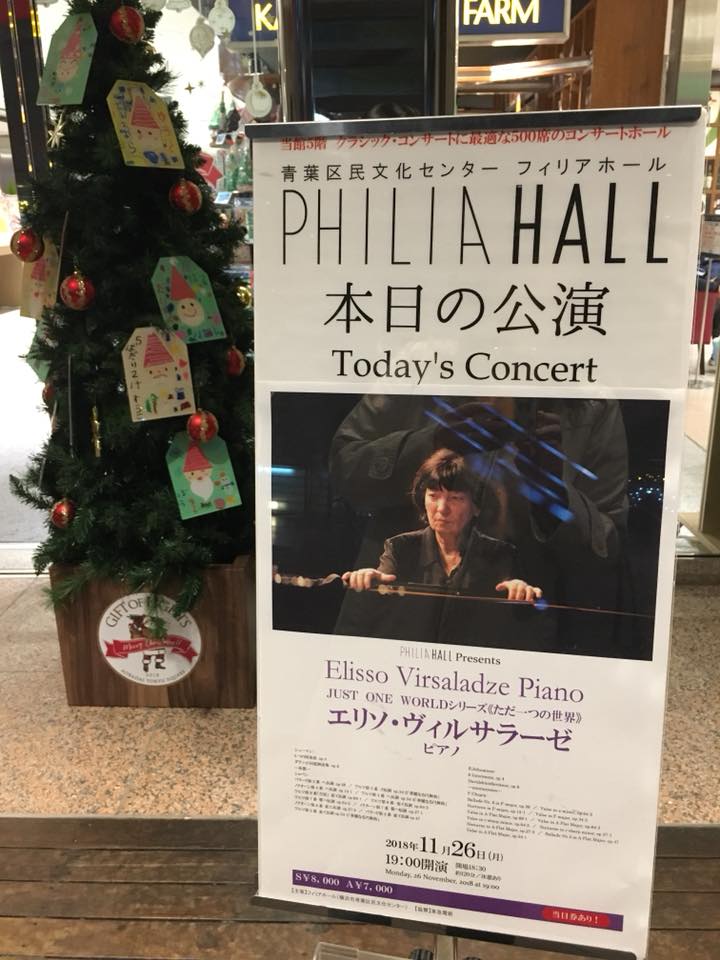【コンサート覚書き】テオドール・クルレンティス&ムジカ・エテルナ初来日
テオドール・クルレンティス&ムジカ・エテルナ初来日
チャイコフスキープログラム
Teodor Currentzis and Music Aeterna – Tchaikovsky Program
@Sumida Triphony Hall
インフルエンザの苦しみがようやく抜け始めてきたので、前から楽しみにしていたオーケストラ ムジカ・エテルナを聴きに行った。世界中で話題騒然、「異端児クルレンティス」「危険な音楽集団」との触れ込みあってか、1800席のすみだトリフォニー大ホールが満席完売。
前半はソリストにパトリツィア・コパチンスカヤを迎えてのヴァイオリン協奏曲で、後半は交響曲第4番。
まず音に色がある。オーケストラだから様々な楽器の色があって当然、というレベルではない。弦楽四重奏や少人数のアンサンブルでのみ実現するような、調性や和声の変化、ニュアンスを大編成のオーケストラで緻密に再現している。
そしてなんと言っても歌い回しのしなやかさ。フレーズの中での音のデクラメーション(増量と減衰)を細部に渡り、また曲全体にも渡ってコントロールしているので、通常オーケストラでは難しい絶妙なルバートと抑揚、切れ味を生み出している。木管楽器の表現力は特筆すべきで、特にクラリネットとフルートは素晴らしい腕前。
ソリストのコパチンスカヤは、噂通り舞台上でスリッパのような靴を脱ぎ、裸足で演奏。終始小鳥がさえずっているようなヴァイオリンで、即興的ではあるけれど極端に音量を落とし過ぎたり、音としての美しさがなく、豊かな響きと表現力を持つオーケストラとのバランスが非常に悪い。フラジオレットやグリッサンドの滑りなど際立った技巧を持っていて、現代曲やジプシー的な民族音楽などには向いているのだろう。稀有で個性的な存在だというのはわかるが、拍感も歌い出しも曖昧で、メロディーラインにチャイコフスキーらしい哀愁、優雅さがほとんど感じられず、大変残念だった。
休憩中、ヴァイオリンとヴィオラ、木管楽器の椅子が全て舞台袖に下げられ、後半は交響曲の間中なんと立ちっぱなし(!)で演奏。それが功を奏し、デュナーミクの幅を与え、音楽に身体全体から生まれる自然な波動を与える。指揮者と同じ目線で演奏することで、当然一体感も増す。金管楽器も吹くときは立奏するので、それに対応するようにだろうか、低弦の多さが目立つなと思って数えてみたら、 コントラバス9本、チェロ14本、ヴィオラ14本だった。(ちなみに1stヴァイオリンは17本、 2ndヴァイオリンが15本)
クルレンティス自身が言うように、「家族のような」団員たちと長時間かけて、入念に徹底した準備をし、これまで弾かれてきた伝統や全体像を把握した上で彼の狙いやこだわりを際立たせるので、説得力がある。久々にオーケストラの演奏に魅せられ、引き込まれた。
終演後、通常は指揮者のみがお辞儀するところを、団員全員でお辞儀するのはとても清々しく、そうするに相応しい演奏だった。
アンコールに、2日後のプログラムの演目である 幻想序曲《ロメオとジュリエット》までそのまま立奏するおまけ付き。15時に始まった演奏会が終わったのは18時近かった。
〔facebookパーソナルページより転載〕