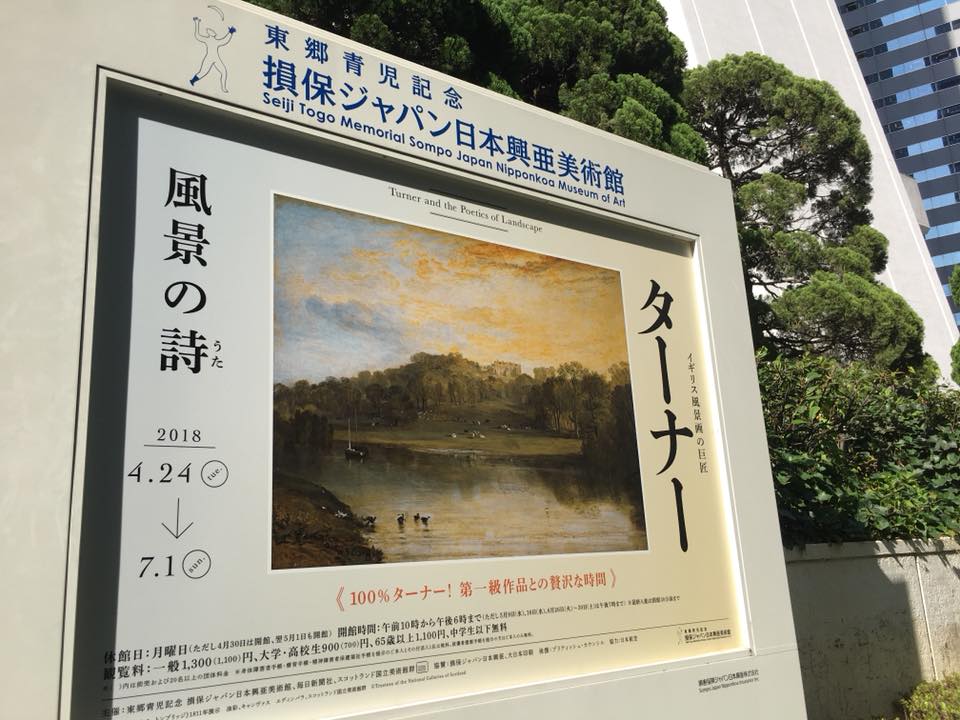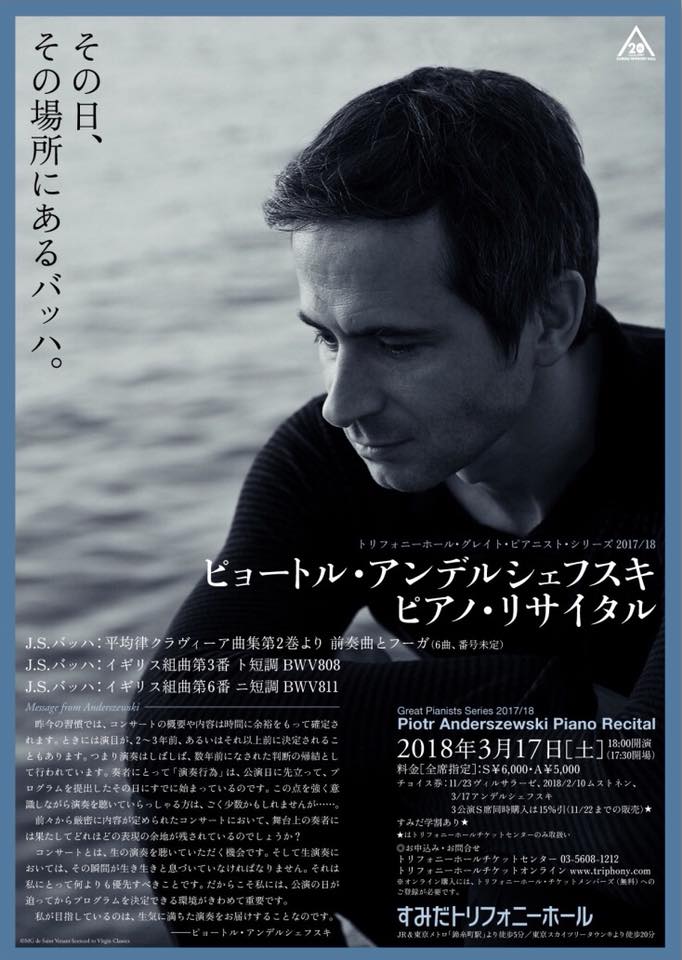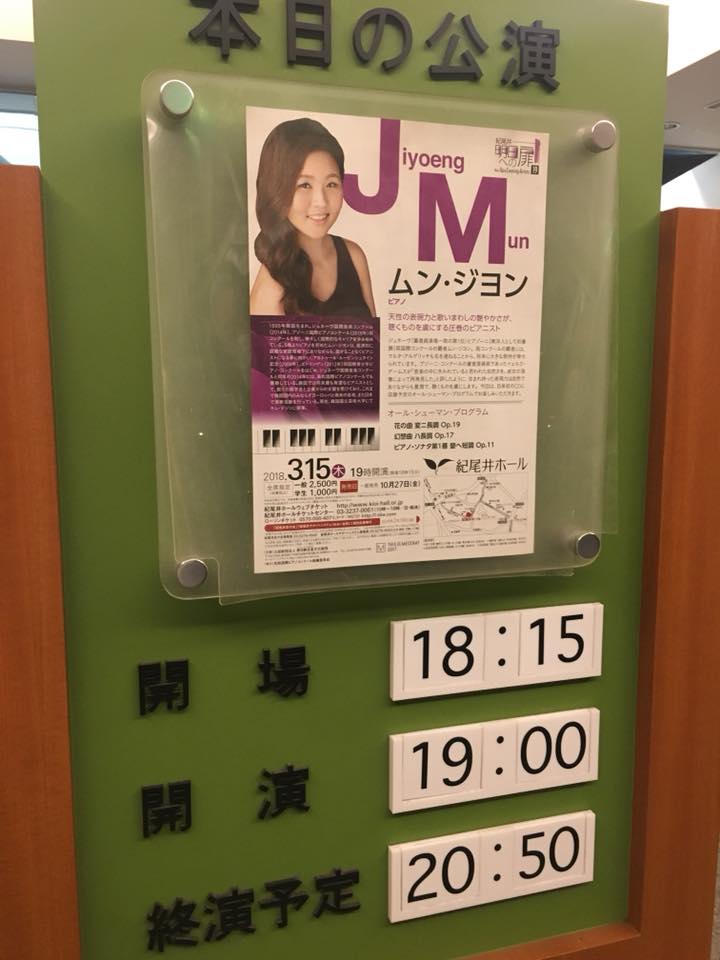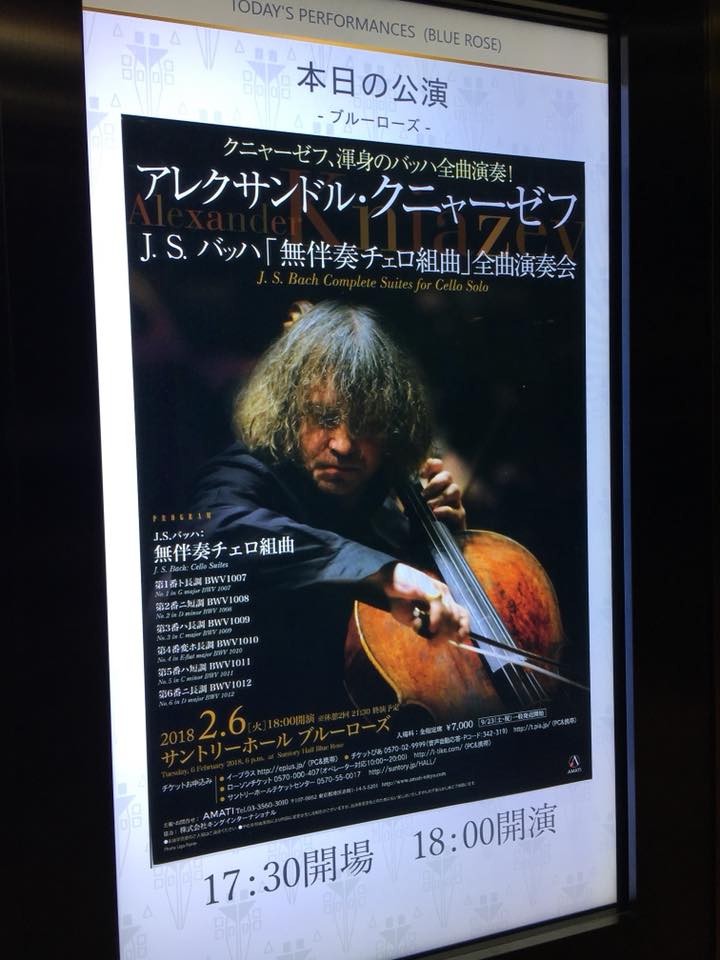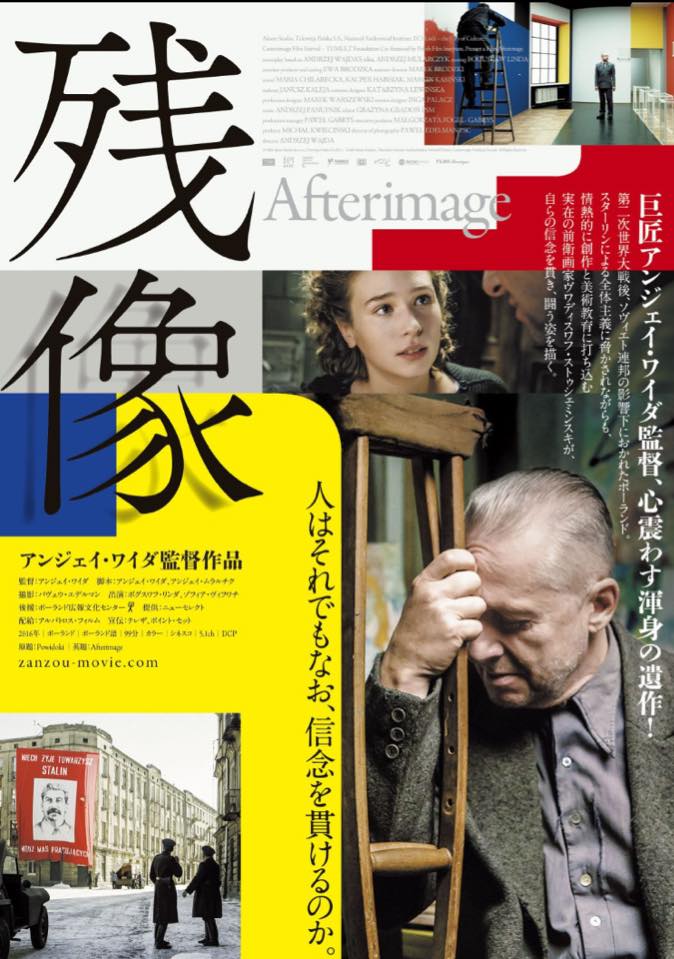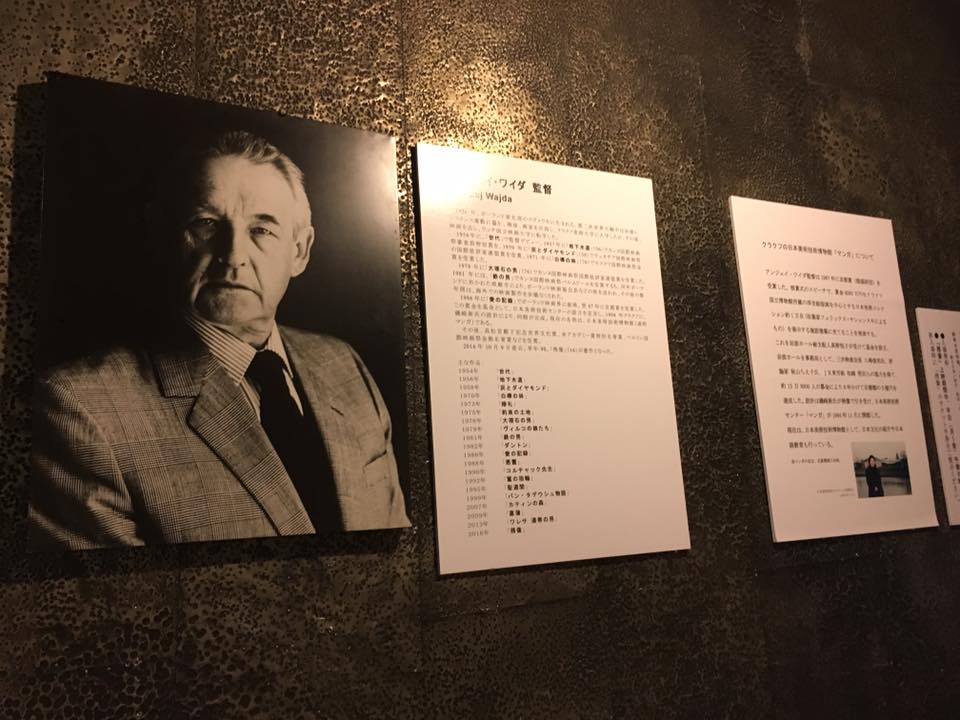【アート覚書き】迎賓館公開とモネ
迎賓館公開とモネ
Public Opening of the State Guest House, Akasaka Palace and Monet’s Legacy
短い夏休みも終わり、早いものでもう9月ですね。
暑い最中に出掛けた、一ヶ月限定の迎賓館赤坂離宮 藤田嗣治天井画特別展示と横浜美術館のモネ〜それからの100年〜展の記憶を辿って…
迎賓館は今から110年ほど前に、大正天皇の東宮御所として建てられた、日本で唯一のネオバロック様式の宮殿で、御所として使用されたことは少なく、国会図書館や政府の行政機関としても使われていたが、その後5年間の改修工事を行い、1974年から外国の賓客のための迎賓館として使用されるようになったそうだ。
この日は特別に夜間のライトアップがあったので、18時に予約を入れておいたのだが、予約確認などは何もなく(荷物検査はありました)並びもせず、すんなりと中に入った。
まず主庭をご覧くださいと、国宝の大きな噴水のある庭に導かれる。夕刻時なので空も美しい色。噴水の側は若干涼風が感じられるが、真夏の都心はこの時間でも汗が吹き出るほど暑い。建物の中は撮影できないからと何枚か写真を撮ったけれど、暑さに耐え切れず宮殿内に入ることにする。
涼しい館内は、一歩踏み入れるだけでその迎賓館としての品位と、装飾や調度品の高級感と、その中で日本的な仕掛けをうまく組み込んだ知恵が施されており、それはそれは絢爛豪華、非常にきらびやかで、お目当てのフジタの天井画がすっかり霞むほどだった。花鳥の間、羽衣の間、彩鸞の間とそれぞれ趣の違った広間があり、各間にボランティアガイドさんがいらっしゃって、気軽に質問に答えて下さる。家具やシャンデリアなどは建設当時からのものだそうで、明治時代に日本でデザインしたものをフランスに発注し、取り寄せたことを考えると感慨深く、その場を足早に去ることはできなかった。ゴブラン織りと見せかけて実は京都西陣織りだったり、壁面に七宝焼が埋め込まれていたり、壁の装飾に西洋の楽器に混じって鼓や琵琶があったり、さりげなく鎧兜が描かれていたり、シャンデリアに金色の鈴が連なって付けられていたり、日本人としての誇り、持て成しなどさまざまな思いが結集された建造物。今回観覧しなかったけれど、「遊人亭」という和風別館が敷地内にあるそうだ。
横浜美術館のモネ展は、クロード・モネとモネに影響を受けた画家の作品が交互に展示されている珍しい企画。主に国内から集められたモネ作品はどれも素晴らしく、特に眩い光を白で表現したジヴェルニー近くの草原の絵や、やはり夕暮れの光の当たり方、空気感を表現した、三重県立美術館所蔵の作品、そして冬のテムズ河の夕暮れを描いた作品に惹かれ、何度も観ては立ち止まった。睡蓮作品も6点ほどあり、モネと言えば睡蓮かもしれないけれど、光を描いた画家なので睡蓮のほうが勝るとは思わない。観る側がその時にが欲しているものに共鳴し、呼応するのだと思っている。個人蔵で日本初公開の、晩年のモネ作品も一点あり、その色鮮やかさにも目を奪われた。他の画家では、写真や映像などさまざまな作品が展示されていたが、ロスコが二点あったのは嬉しかった。
〔facebookパーソナルページより転載〕