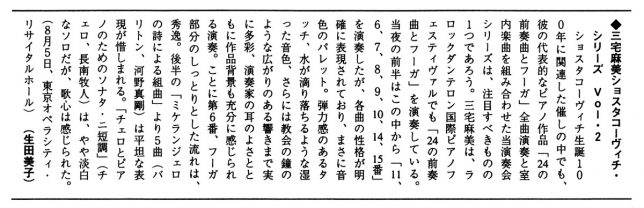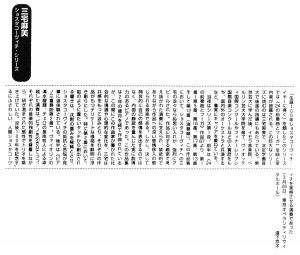三宅麻美 ショスタコーヴィチ・シリーズ Vol. 5

三宅麻美 ショスタコーヴィチ・シリーズ Vol. 5
相貌の違いを堪能
ピアニスト三宅麻美が2006年からショスタコーヴィチ・シリーズを行い、ピアノ曲「24の前奏曲とフーガ」をはじめ、室内楽曲や歌曲のジャンルにまで踏み込んだ意欲的な演奏を聴かせてきた。シリーズ最終回で組んだプログラムは、10代、20代に作曲されたピアノ独奏曲と晩年の「ヴァイオリン・ソナタ」。出発・終盤両地点で見せる(聴かせる)作曲家の相貌の違いを目の当たりで堪能する刺激的なコンサートとなった。
まるでしゃれた前菜を供するように小気味よく聴かせた「三つの幻想的舞曲」。10代半ばにして才気煥発[さいきかんぱつ]、モダンな感覚にあふれたこの小品や、つづいて演奏された20代の曲「24の前奏曲」からは、後の作品に見られるような屈折した韜晦[とうかい]はまだ聴こえてこない。順風満帆とまではいかないが、作曲人生を歩み始めた若いショスタコーヴィチのみずみずしい息吹が、音やリズムの個性的表情から生き生きと聴こえてくる。各曲の性格的な特色をつかんだ演奏がその変幻多彩な面白さをよく引き出して、聴く者を飽きさせない。
一方、作曲家の多事多難な人生が深く刻印されているかのごとき「ヴァイオリン・ソナタ」は、「前奏曲」と同じようには聴けない。レクイエムとも葬送の音楽とも聴こえるこの作品で、作曲者が自分の死について考えていたことは間違いないだろう。ゆるやかなテンポで静謐[せいひつ]な緊張感がつづく両端楽章にはさまれた激烈なスケルツォ楽章は、あたかもディエス・イレ(怒りの日=レクイエムの重要部分)のごとし。うってつけの共演者・荒井英治の渾身[こんしん]の演奏と掛け合わされた迫真のデュオは聴き応え十分。シリーズのとどめにふさわしい快演となった。
(池田逸子・音楽評論家)
5月23日、東京・王子ホール